|
17歳の一冊
テレビで芸能人がそれぞれ、「私の感動した本」を紹介する番組があった。サン・テグジュベリの「星の王子様」、サリンジャーの「ライ麦畑でつかまえて」、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」、夏目漱石の「三四郎」などなど……。
大体読んだことがあるけれど、私はそんなに感動はしなかったな、なんて少し醒めた気持ちで見ていた。そして、私にもそんな一冊はあったのだろうかと自分を振り返る。
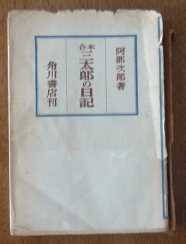 あるある、阿部次郎の「合本三太郎の日記」を思い出す。どこかにあったはずだ。書棚かき回してやっと見つける。長い時の流れの前ですっかり黄色を通り越して褐色に変色し、表紙もぼろぼろになっている。
あるある、阿部次郎の「合本三太郎の日記」を思い出す。どこかにあったはずだ。書棚かき回してやっと見つける。長い時の流れの前ですっかり黄色を通り越して褐色に変色し、表紙もぼろぼろになっている。
そう言えばこの本は、一時は何度も続けざまに読み返したけれど、その時期を離れてからは改めて読み返した記憶がない。そうだとすれば、この本の裏表紙に「1957(昭32)3月11日、夕張市鹿の谷、堀江書店」とメモしてあるから、今から46年も前の高校2年生以来ということになる。
角川文庫A5版400ページ余、定価200円。「へぇー、この当時は文庫本ってこんなサイズだったんだ」と変なところに感心している。
3月11日と言えば、高3直前の春休みだろうか、17歳の多感な青春の片鱗が確かにこの本には閉じ込められている。
あちこち赤鉛筆で線が引いてあり、また、常用漢字には無く、この本以外では使うことなどないだろうと思われる理解できない漢字には、ページの余白に読みかたとその意味が下手な字で書きこんである。どこまで理解していたのかは分からない。恐らくは何も理解していなかったと思う方が正しいのだろう。
・ 神秘の深さは求める心の強さに比例するものだろう(P421)
・ 我等は偉人の研究に当たっては、特にこの不一致の要求を模倣することを慎まなければならない(P302)
・ 俺の求めているのは一貫せる意志の連続である。思想と思想との緊密なる連続である。ひきくるめて言えば生活内容の連続である(P188)
・ 凡ての立場にはそれぞれに限られた視野がある(P260)…
赤鉛筆のないページを探す方が難しいほどだし、最後のページまで引いてあるから、よほど繰り返し読んだのだろう。多分にペダンティックな気持ちが強かったような記憶があるし、17歳に理解できるようなものではないことは、今パラパラとめくってみても良く分かる。
それでもこの本からは、多くの影響を受けた。阿部次郎の考え方とか思想に影響を受けるほど、私に理解力があったとは思えない。むしろ著者が使っている言葉(熟語)や表現の仕方などが、その後の私の作る文章に大きく影響を与えているというのが正直な感想である。
もちろんそれは一種の模倣であり、模倣することで自分が阿部次郎もどきに変身できるのではないかという、きわめて単純な動機に基づくものであったろう。それはやがて錯覚であると分かることになるのではあるけれど、変身できると思い込むこと自体が若さであり、たとえ虚栄の衣であろうともそこに包まれたいと願うのもまた、地に足のついていない若者の特権でもあったのだと思う。
「人はニュートンにはなれないかも知れないが、ニュートンの肩に乗ることはできる」。だれの言葉だったか忘れてしまったが、なんという心地よい響きを持っている言葉だろう。人は過去を学ぶことによって、その上に自分を積み重ねていくことができると言う。それはどんな場合でも人は僅かの努力で進歩できると語ってくれているのである。
でも本当は違うのである。ニュートンの肩先に乗ることのできる者とは、ニュートンを理解した者でなければならないのである。そしてニュートンを超えるような努力をしたほんの僅かの者にしか、肩先に乗ることは許されないのである。
かくして似非哲学者の道を目指した若者は、数語の哲学用語を身の内に残したまま、常識の世界を歩いて行くことになる。それでいいのである。その程度の理解しかできなかった者としての、それなりの満足した人生だったのである。
少しカビの匂いのする茶褐色のこの本のページをめくりながら、「この歳になってもやっぱり理解できないや」と、40数年の時の狭間のあまりの長さに嘆息しつつ、人は努力しても駄目な場合があるし、ましてやそんなに一生懸命な努力をしなかったこの身にとってみれば、それは当然の経過と当然の結果なんだと、黄昏に近づいている自分を慰めているもう一人の自分がここに居る。
|
|