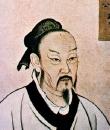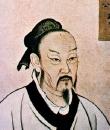確かNHKの学校向け番組の一つだったと思うのだが、アニメ入りでことわざの解説をしているのを見た。数字の入ったことわざをいくつか並べた番組だったように気がしているので、特にこの言葉に特化しているとは言えない内容だった。その時並べられていた一つが、このエッセイのタイトルにした「五十歩百歩」であった。
中国の孟子の言葉で、ある戦闘から逃げ出した甲乙二人の一方が他方を、お前の方が五十歩多く逃げたから私よりも卑怯だと批判したと言う言い訳をめぐる話しだったから、その意味は正しく伝わっているように思えた。つまり「どっちにしたところで似たり寄ったり」と言う解説はそれなり正しい解釈を示していたと思えたのである。ただ、そうした正解にもかかわらず、見ていてどこかに抵抗感が残ったのは、いつもの私のへそ曲がりが頭を持ち上げてきたからなのかも知れない。
それはこうしたことわざの意味を知りつつも、五十歩の差というのはとても大きい、もしくは貴重な場合もあるのでないかと思えたからである。五十歩百歩の差である五十歩は、その数値そのものに意味があるわけではない。つまり五十五歩だろうが四十五歩だろうが「一方が他方より多いか少ないか」だけに意味を持たせ、その差があることだけをもとに一方が他方を批判できるかどうかを問題にしているだろうからである。
相対的にはゼロ点から計測した百歩と五十歩の者の差と、例えば千歩を超える百歩と五十歩の者との差とでは多少意味が違うようにも感じるけれど、そこまで詮索する必要もあるまい。
私が感じたのは、少なくとも現代では差の大小は、それがたとえ数歩にしろ数点にしろ数メートルにしろ、更には数秒にしろ無視できないまでの差として現れてくると言う事実が存在しているのではないかと思ったからである。そうした僅少であっても差は差であるとして認識するような時代が正しい世の中なのだと必ずしも信じているわけではない。だがそうした僅かな差が、片方を成功者へと導き他方に失敗者としての烙印を押すような例が事実として存在していることを言いたかったのである。
少子化の下で定員を下回るような大学が発生しているけれど、多くの大学の合否は入学試験の得点が高い方から決定される。もちろん面接や高校時代のクラブ活動や論文の文章力などと言った評価を加えて決定している例のあることを知らないではない。それでも、つまるところそうした評価も得点化され、合否の決定はその得点の高さが基準とされるのではないだろうか。具体的な例として知っているわけではないけれど、一点の差の中に数十人の受験生がひしめいていると聞いたことがある。
むかし独学で統計学を学んでいたときに、正規分布曲線と言う考え方のあることを知った。ある集団を階層に分けるとき、平均付近に多くの人が集まり両端に近づくにしたがって少しずつ少なくなっていくという法則である。それは一つの仮定ではあるのだろうし、それを平均値と標準偏差を因数としたなだらかな山形曲線に当てはめることがすべてに妥当するとは必ずしも思えない。
それでも例えば試験結果で言えば、満点は一人、90点台が10人と少しずつ増えていき、平均点の回りに一番多くの人が集まり、そしてまた少なくなっていって零点が一人となるような分布は比較的考えやすいだろう。
さてこうした時、合格ラインを50点に決めたとしよう。つまり50点なら合格だが、49点なら不合格と言う意味である。合格者数はあらかじめ決められているのだからどこかで区切らねばならず、こうした判定は合理的ということになる。さてここに50点の受験生が30人いて、49点が20人いたとしよう。ここでは五十歩百歩などと言う言い訳は通じない。一点の違いが合否を分けることになる。恐らく観念的には50点の受験生と49点の受験生との間に、合格不合格の差ほどに学力の違いはないであろう。「どちらも似たり寄ったり」はまさにこうした場合にも至言であるように思える。
だが49点の受験生の名は掲示板に載ることはない。その受験生は少なくともこの学校に関しては敗北者として位置づけられることになる。私はそのことの適否や不合理を言いたいのではない。「似たり寄ったり」なのだから合格させたって言いじゃないかとの意見があるかも知れないけれど、世の中にはどこかで線引きしなければならないことがいくらでもある。
例えば私の仕事である税理士だって、決められた申告期限、納付期限、申請期限などと言った多くの「期限」の下で仕事をしている。台風や災害などの特別な事情がないにもかかわらず、ある書類が期限までに提出されなかった場合、その申請が却下されたり様々な特典が受けられなくなったりする。5月31日の午後11時59分と6月1日午前0時とはまさに「似たり寄ったり」である。もっと言うなら密着しているとも言えるだろう。それでも午前0時を回ったことで法律で決められた期限を過ぎたことは否定のしようがなく、遅れたことのペナルティは提出者が負うことになるのである。
マラソンでも100メートル競争でも、今や100分の1秒単位で計測されるようになった。サッカーでの得点も残り時間が0と表示されるまでにゴールへボールを入れなければならないし、ゴルフは相手よりも一つでいいから打数を減らさなければならない。
世はあげて勝者の時代である。富士山は日本一だから人々の記憶に残る。だが日本で二番目に高い山について知る人は恐らく小数であろうし、日本で二番目に長い川も同様であろう。一点でも、なんなら0.5点でも、100分の1秒でも、他より差をつけることが今や正義になってしまっているのである。そしてその差に遅れた者は自動的に敗者となり、場合によっては忘れ去られてさえしまうのである。
現代は、それが正しいことだとは思わないけれど、「似たり寄ったり」をひとまとめにして「差がない」などとのんびりしたことなど言っていられない時代になってしまったのである。五十歩逃げた者は五十一歩の者よりも勝者になれるかも知れないのである。
五十歩百歩の俚諺は、恐らく一歩も逃げなかった者が多数存在している場合にのみ意味を持つのではないだろうか。もし仮に全員が逃げ出してしまったとしたならその軍隊は丸裸である。それでも指揮官がどこかで立て直しを図るべく兵隊を再編しようとするなら、私なら逃げた全員を「似たり寄ったり」の頼りない存在として解雇し自分ひとり丸裸のままで敵に挑むよりは、まず五十歩に止まった者の中から順に兵士を選ぶのではないかと思うのである。
それは一歩にしろその差を勇気の差、マイナスではあるけれど「負が少ないことの差」として認識したいと願うからでもある。
昔読んだ本の中にこんな話しがあったのを思い出した。ある会社の女子社員の採用試験で、面接会場のドアを開けたところに紙くずを置いたそうである。受験生がその紙くずをどうするかを観察するのだそうである。拾い上げてポケットに入れる者、どうしましょうかと面接官に聞く者、無視して避けて通り過ぎる者、時には部屋の隅に蹴っ飛ばす者など様々だったそうである。
その話を聞いた面接官の友人が、「無視したり蹴っ飛ばしたりした子は採用しなかったのかい」と聞いたそうである。それに対して面接官だった彼は「そんなこと気にしていたら採用できないからね。紙くずとは無関係に決めたんだ」と答えたそうである。
2010.5.10 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ