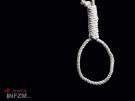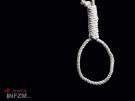例えば死刑執行人がいる。世界には死刑制度を認めていない国も多いけれど、日本は古来から死刑を刑罰の最高刑として維持してきた国である。だから死刑判決も年に数件は下されている。もちろん、死刑の判決が下されることとその犯罪人が死刑に処せられることとは別である。正確には知らないけれど、現在でも100人前後の確定した死刑囚が拘留されていると聞く。その原因は刑事訴訟法で「①死刑の執行は、法務大臣の命令による。②前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。・・・」(475条)と定められているにもかかわらず、法務大臣の職務怠慢かそれとも内心の意思によるものなのかは不明ながら、執行書へのサインが遅れているせいだと言われている。当然ながら再審請求などで執行が延期されているケースも中には存在しているだろうけれど・・・。
そうした遅延の原因はともかくとして現実に死刑が執行されていることも事実である。私は死刑執行の手順を必ずしも理解しているわけではない。「死刑は、監獄内において、絞首して執行する」と刑法11条は規定しているから、その通りに行われるのだろう。だがその執行に対して立会人などの規定はあるけれど(刑事訴訟法475条以下)、直接執行する者の選定方法や執行の手順などを定めた規定は見当たらない。それは恐らく上司に命ぜられた特定の者によって、何らかのスイッチを押すのかハンドルを引くのか、それとも連動する踏み板に足をかけるのか・・・、いずれにしてもある特定の個人の特定の行為によって死刑囚は絞首の方法で死を迎えることになる。
さてこの背後に存在する死刑執行人についてである。検事が死刑を求刑し、裁判官が死刑の判決を下し、法務大臣がその執行を許可したところで、彼等自身が死刑執行のスイッチを直接押すわけではない。ところでそのスイッチを押した者は、果たして「人を殺した」ことになるのであろうか。確かに死刑の判決や死刑執行の署名があったにしろそれはスイッチを押せと命じただけにしか過ぎず、事実として人が死んだのはスイッチを押した彼がその行為をしたからである。だがそのことを「人を殺した行為」だと言い切っていいのだうろか。
その者の仕事(この他にも日常的にやるべき仕事は多く存在しているだろうが)は、ある動作によって死刑囚の死刑を執行することである。被害者がいて加害者が逮捕され、更に多くの人たちがかかわって裁判官は死刑を宣告し、場合によって高裁、最高裁、再審請求などを経て刑が確定する。そしてやがて執行の時を迎える。さてその死刑を具体的に執行するのは恐らく公務員であろう。さて彼は「人を殺した」のだろうか。
人には多くの人生がある。色々な思いを抱えながらもスイッチを押すと言う仕事を終えた者が確かにここにひとり存在している。また別に、スイッチを押す仕事ではなかったけれど、きつい一日の労働を終えて一風呂浴びてビールを傾け一息ついているもう一人がいる。二人の男はどこが違うのだろうか。ビールを飲みながら家族と談笑している男の集団に、スイッチを押した男を入れることはできるのだろうか。
人は、情熱や愛や憎しみ、更には名誉や復讐のために人を殺すことがある。もっと別に、金持ちになるためや権力を得るために他者の命を奪うことだってあるだろう。そしてその延長に革命であるとか戦争などが続くであろうこともまた否定できない事実である。そうした意味での「人を殺す」ことと、刑罰としての死刑とは違うであろうことを否定するつもりはない。
それはそうなんだが、そうした違いはスイッチを押すことの動機の問題であって、それに続く「人が死ぬ」ことに関しては少しも違うところはない。単に判決の執行なのだと割り切ることができるのだろうか。戦闘などで人が死ぬことも多いだろうけれど、例えば世界には粛清という名を借り、裁判というシステムを経た上での大量虐殺だって過去にも、そして今でも確実に珍しくなく存在している。
恐らく死刑のスイッチを押す行為は、いわゆる刑法における正当行為として位置づけられるものであろう。床屋が髪の毛を切るのも、警官が逮捕状を手にして人の自由を拘束することも、医師が手術で患者の体を切り開くのも、外形的には傷害や誘拐の状態を示しているにもかかわらず正当行為に該当するとして免責されるのであろう。
刑法は犯罪の不成立・刑の減免として正当行為(35条)、正当防衛(36条)、緊急避難(37条)を掲げた。正当行為とは「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」とされるものであり、死刑の執行もまたこの範疇に含まれるであろうことに異論はない。それにもかかわらず死刑の執行に「人を殺す」ことの意味を重ねてしまうのは、死刑制度そのものに対して私がどこかで違和感を抱いているからなのだろうか。
「人を殺す」とは、「人を殺す意思を持って人を殺す」ことであろう。そうした意味では、仮に手術によって患者が死亡したとしても、そしてそれが危険で助かる確率が極めて低い手術だったとしても、その患者の死は医師が「人を殺す意思を持って執刀した」ことによる死ではない。それはまさに「死んだ」のであり、「殺した」のとは違うからである。だが死刑はこれとはまるで違う。執行者は明確な殺す意思の下にスイッチを押したはずだからである。命とは一体何なのだろうか。「殺す」とは誰がどんな風に決めるのだろうか。
私は「死刑の存続か廃止か」を問われるような場面に直面したとするなら、恐らく多少の迷いは残るにしても「存続」を選ぶような気がしている。それはたとえ死刑の執行によって殺された人が生き返ることはないにしても、殺された者やその親族の抱くであろう無念さを感じるからだと思う。そしてどこか「殺した者」にはそれと同じような報復を受けること、つまり「目には目を」みたいな対応がふさわしいとの気持ちを捨てきれないでいるからでもあろう。
いやいやもしかしたらそれ以上に、距離感のある死は、死そのものの実感からも遠くなってしまうからなのかも知れない。飯を食いながら、場合によってはグラスの酒を口に運びながら、突然にテレビで流される死刑執行のニュースを知る。死刑囚が犯した事件の概要や判決の経緯などがコンパクトに流される。数分の報道でニュースは次の事件や政治や天気予報などへと変わっていく。その死刑報道に、私の持つグラスの酒は揺らぐことすらない。その死は私からは遠く、無縁な死でしかないからである。それはまた被害者や親族などが抱くであろう殺された無念への共感と、加害者が死刑によって奪われた命への共感とはまるで重みが違うと感じているからなのかも知れない。
作家辺見庸は死刑を国家の演出の儀式であるとし、その制度に日本人は口をつぐむと表現した。そしてその日本人に自らも含まれることを重ねつつ。
「
・・・セケンを背にした死刑という表現はかくも繊細であり、陰影に富み、これを美とするか醜とするかはべつにして、あくまでもジャパネスクなのであり、私たちの心のありようにしんしんとつながつている。同居する犬が死んだら私はたぶん、さめざめと泣くであろう。しかし明朝だれかが絞首刑に処されるのを知るにおよんでも、悩乱をつのらせることはあれ、涙を流すまではすまい。私もまた悲しむことのできる悲しみしか悲しんではいないのだ。今日もまた私はふうふういいながら左手で犬のトイレを掃除する。犬と眼が合う。私はなごみ、同時にぞっとする。日常がこれでよいわけがない。そう自答する。」(2009.6.17、朝日新聞、寄稿「犬と日常と絞首刑」)
麻薬犯罪に関して中国で逮捕され死刑を宣告された日本人に対して、6日に一人、9日に三人と、この4日間で四人もの死刑が執行された。日本では決して死刑にはならない程度の犯罪だとしてマスコミは取り上げているが、彼我の制度の違いはあるにしても、猟奇、残虐、無差別など最近の日本の殺人もどこか不気味なエスカレートを見せているような気がしてならない。死刑廃止を選択している国は多い。日本人にも「犯罪を許す」との意味からではなく、違った観点から刑罰としての死刑を考え直すことが果たしてできるのだろうか。
2010.4.9 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ