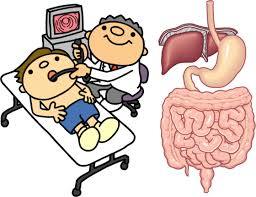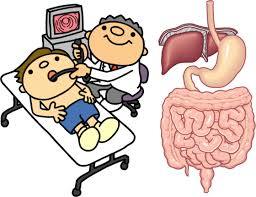最近、がん検診を取り上げたテレビ番組を見た。70歳ほどの老女が手術台に横たわっている。がんを直接切除するための手術ではなく、生検だという。がんの性質や浸潤の程度を調べるのか切り取る範囲を決めようとしているのか、そこまでは分らない。ただ、がんの部位にメスを入れて腫瘍の一部を切り取り、リンパ節への転移なども含めて検査するとのことであった。手術はそこまででいったん中止し、切り取った部分の精密検査を経て今後の治療方針を決めようとするものである。
そのことに異論があるわけではない。CTにしろMRIやPETなどの検査にしろ、はたまた血液検査や内視鏡による検査にしろ、いわゆる間接的な検査にとどまるのであろうから、手術で患部を目の前にするのとはどうしても違いがあるだろうからである。だから、患者の肉体的精神的な負担はともあれ、直接的な手術に近づけるような検査が望ましいことは言うまでもない。
私が気になったのは、この検査結果を患者に知らせる医者の態度であった。私はこの医者の態度を見て、「ああ、医者というのは矢張り患者とは別次元の生物なんだな」と感じたのである。この医者が人格的に尊敬できないとか、思いやりがないとか、更には人間性に乏しいなどと思ったわけではない。むしろ、当たり前の応対だと思い、だからこそ患者と医師の立場の違いというものに改めて気づかされたのである。
もちろんこの場で対峙しているのは患者と医者の二人だけである。そして一方は無知の患者、一方は専門家でありかつ裁判官である。この両者を対等と感じること自体が間違いなのかも知れない。被告と裁判官の対峙する場面を想定してしまうこと自体、始めから両者の権力関係を間違った方向へ誘導してしまっているのかも知れない。でも私は、少なくとも患者自身が医師の前に立つ己の位置を、間違っているいるにせよこのように規定してしまっていることを、否定できないように思っているのである。
患者の立場を考えてみよう。少なくともこの患者は「がん」であることの告知を受けている。ただどのように治療していくかを決めるため、小さな手術で検査をしたのである。そして今日がその結果を知らされる日であり、結果を知らせるべく医者が目の前の椅子に座っているのである。恐らく数時間前に自宅を出て、バスと徒歩で病院に着き、待合室で待たされ、やっと今順番が来たのである。
がんを余生を自分の意思のままに過ごすことのできる時間を与えてくれる、どちらかというと恵まれた病気であると思う人がいないではない。それでもその前提となっているのは、「がんは死の病である」という観念である。もちろん医療技術の進歩により、いわゆる「治るがん」も増えてきているのは事実である。「がん=死」方程式は必ずしも成立しない時代になってきている。
それでも、多くの人、むしろ告知された全部の人が、一度はこの「がん=死」の方程式を頭に浮かべるのではないだろうか。それは日本人の死因のトップががんであり、また「自ら死」について考えさせられる時間を強制的に与えられてしまうのががんだからである。
この患者もどこまで覚悟したかは分らないけれど、きっと「自らの死」を意識したはずである。それは少なくとも「がんを告知された」その時から始まり、そして今口を開こうとしている医師を目の前にしているときも続いているはずである。医者から死刑宣告がされるとは思わないにしても、いまここでテーマとなっているのが「自分の死」についての話題であることは自覚しているはずである。
そんな患者に医師は淡々と伝える。それは奇をてらう必要もないし、誤魔化すつもりもない、単なる事実の羅列に過ぎないことである。医師にはなんの気負いもなく、この患者の直前に診察した患者にも同じように接していることだろう。
まず最初、①調子はどうですか、と声をかける。それはいいだろう。次の言葉は、②がんは一部が粘膜下層にまで浸潤しています、であり、更に③ここに入るとがんはリンパ節に転移する能力を持っている、④32個のリンパ節を採ったのでそれを調べました、⑤その結果転移は見られませんでしたと続く。
このことに私は気になったのである。医者の説明が分らないではない。経過とその結果を淡々と述べているに過ぎない。その順序も経過も簡潔でよく分かる。でもそれは私が当事者でないからである。私ががん患者としてこの医師と向き合っているわけではないからである。視聴者のほとんどが傍観者である。それを私は見ている。番組の意図も説明もよく分かる。番組の目的さえも分るような気がする。
でも違うと思ったのである。この医者は視聴者と話しているのではない。話しているのは目の前の一人の患者なのである。患者が抱いていることは、単なる不安だけである。がんがどんな顔をしているのか、どこまで広がっているのか、そんなことはどうでもいい(とは言わないまでも、今必要なのは学術用語ではなくこれからどうなるかである)、「私はこれからどうなるの」なのである。
この検査によってがんが直ちに治るわけではない。場合によっては、「検査の結果、がんではありませんでした」、「このままお帰りください」ということだってあるかも知れないけれど、恐らく長い闘病が続くだろうことは患者も承知していることだろう。「助けて欲しい」、「なんとか治して欲しい」が、患者の唯一の望みであろう。その途中経過を聞くために、ここにきたのである。医師の答を聞きたいのである。たとえそれが自らの思いを否定する答えであろうとも、である。
私にはどうして医者が結論である⑤の「転移はありませんでした」を最初に患者に知らせなかったのだろうかと、疑問に思えて仕方がないのである。②~④がどうでもいいとは言わない。だが患者が聞きたいのはまず④だったと思うのである。④だけだったとすら思うのである。②~④の説明は、その後からでも遅くはなかったのではないかと思ったのである。
裁判官だって、まず主文で結論を述べてから理由に入る。それが「死刑」にしろ「無罪」にしろ、まず結論たる「主文」を告げることが、裁判という制度の基本だと認識しているからである。理由や事実認定や判断経過がどうでもいいというわけではない。一番の目的が、そして被告にしろ原告にしろ、さらにはこの裁判にかかわった検事や弁護士や、もっというなら傍聴人までも含めた多くの人が、一番要だと思っているのが結論たる「主文」だと認識しているからでもあろう。
患者と医者とは立場が違うことは分っているつもりである。また、経過があってこその結論だという意味もよく分かる。でも「患者が今何を一番聞きたがっているのか」を理解する医師を患者は望み、そうあってこそ、患者と医師の会話なり意思疎通が図られていくのではないか、そんな思いでこの番組を見ていたのである。そしてこの患者と医師という両者に、超えることのできない立ち位置の違いというものをあからさまに見せ付けられたような気も同時にしたのである。
「もし自分が患者だったら」、こんな思いからの視点がこの医者には不足しているように思えてならない。今日の話題は「がん告知」そのものではないけれど、「がん告知」後一週間以内の自殺率は一般の約12倍、心疾患による死亡は約5倍にも及ぶとの話を聞いたことがある。「がん=死」の方程式は、それほどまでに患者にストレスとして浸透しているのである。相談センターや患者会でそれなりの対応をしているのかも知れないけれど、患者はそうした事実さえ知らないまま告知を受けることだってあるのである。まず医師が予め「告知の受容」の心構えを患者へ向けてやることが必要になるのではないだろうか。
こうした「相手の立場や気持ちを思いやる」というささやかな視点の違いは、患者と医師という範囲を超えて、もしかしたら世の中全体に思ったよりも高い障壁として存在しているのかも知れないと思ったのである。そして人は立ち位置の違いという壁を思うほど簡単には乗り越えられないのかも知れないとも感じたのであった。
2016.2.24 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ