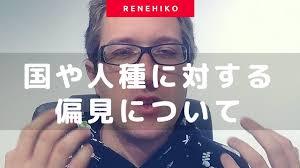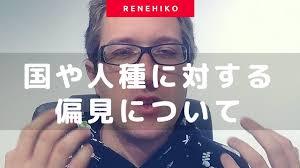今週のエッセイは、二本続けて新聞投稿を取り上げることになってしまった。まあ、それだけ私自身の情報入力の手段というか、社会と付き合う範囲が狭くなってきていることの証左なのかもしれない。
気になったのは「国籍だけで入店お断りとは」と題する投稿(2018.1.16 朝日、東京都 25歳男性)についてであった。
投稿者には付き合っているドイツ人の彼女がいて、目下一緒に住むための部屋探しの最中である。その途中で、家主からなのか不動産業者からなのかは分らないけれど、賃借を申し込んだ相手から「外国籍の人(への賃貸)は断っている」と言われて断られたことに対する批判である。縷々書いてあるけれど、つまるところ「人種による差別や偏見は許されない、もっと心を広く持て」との主張である。
恐らく誰もが彼の主張に賛成するだろう。入居を断った業者が悪いと誰もが思うだろうし、断るべきでなかったとも主張するだろう。そのことは良く分る。私自身だってこんな話を聞いたたら、恐らくそう思うだろう。それでも私には、見たことも会ったこともない貸さなかった家主の気持ちが、投稿者の気持ち同様とても良く分るような気がしたのである。
投稿者の言い分も正しいし、それと同時に家主の言い分も分かるような気がしたのである。それは別に人種差別を承認したいというのではない。また自分の持っているアパートを誰に貸そうが、それは家主の所有権の範囲内の問題で勝手ではないかと、論点をすりかえようとするつもりでもない。
私が家主の抱いた「外国人お断り」の内心が理解できるように思ったのは、私たちが抱いている第一印象に左右される習癖によるものだと思うからである。
私たちはどんな場合も第一印象を大切にすることを自らに課し、また他人にもそのように助言するのを常としてきた。第一印象とは、まさに「見かけ」による判断を指している。対面している相手が、優しいか、怖いか、信用できそうか、ずる賢こそうか、何歳ぐらいか、お金を持っていそうかなどなど、人は見かけで判断する。しかもその判断がどこまで正しいかは保証の限りではない。
どうしてなのか。それは人は見かけでは分からないからである。見知らぬ者を見かけで判断して、結果的にその判断が誤りだったことは、私たちは長い人生で数多く経験しているはずである。見かけで人は分からないことを、私たちは口惜しいほどにも身に沁みて知っている。
それでも人は見かけを気にし、見かけで他者を判断しようとする。それは、我が身への危険を避けるための必須の要件だからである。見知らぬ他者が私に危害を加える恐れがあるかないか、それを咄嗟に判断するために、人は見知らぬ他者の見かけを頼りに判断しなければならなかったのである。たとえその判断が間違いだったとしても、その判断をよりどころに自らの危険回避を図らねばならなかったのである。それが生き延びることであり、生き抜くことだったからである。
見かけによる咄嗟の判断は、自らの危険回避が主なる目的である。だが同時にその判断が誤っていた場合は、その他者へ言われなき危険や損失を負わせることになる。つまり、「見かけによる判断」というのは、常に「自らの危険回避」と「その他者に対する言われなき偏見」とのせめぎあいで成り立っているのである。
だとするなら、「見かけでどこまで真実が分るか」がその基本的な判断基準になる。「見知らぬ他者を恐れる」、「とりあえず危険と診断する・・・」とは密接不離であり、その判断に伴う危険負担は、例えば投稿にあるような貨家を持つ家主が自ら負わなければならないことなのである。
汚職警官が続発し、わいせつ教員が連続する。そんなとき、「どんな時にも正しい警官はいる」、「熱血先生はどこにでもいる」、「悪いのは一握りであって、多くの警官や教員はまっとうだ」などの異論が繰り返される。確かにそうだろう。仮に、90%の警官や先生が悪人だとしたところで、残る一割はまっとうな警官であり誠実な先生であることに違いはない。
それでも「人は見かけじゃ分からない」のである。優しそうで親切そうに見える人が常に善人とは限らない。二の腕に刺青があり、恐持てでヤクザのような顔つきの人物が常に犯罪者だとは限らない。だから人は、数人の警官の不祥事や数十人の先生の猥褻事件をもとに、「今時のケイカンは・・・」とか「今時のセンセイ方は・・・」と断じてしまうのである。
だとするなら、僅か数人の起こした事件で全体を判断してしまうのだから、残る「悪くない多数」にとってみれば、まさにその判断は偏見である。
偏見が相手を傷つけることのあることは良く分る。だがそれは、公正な立場で「偏見であることが分っている場合」、「証明できる場合」に成立することなのである。「家賃をきちんと払えそうにないように見える」とか、「家賃の請求をしても、外国人では話が通じなくて回収できないかもしれない」などと家主が考えたとき、そう考えた家主の判断が正しかったとしたなら、仮に賃貸を断ったとしてもそれを家主の偏見とは言わないだろう。そしてそこに「人は見かけでは分らない」という要素が重なるのである。
一事を以って万事を断ずることは、まさに偏見であろう。でも私たちは偏見で生き延びてきたのである。偏見は言葉を代えるなら「気配」である。「直観」である。なんなら「合理的推論」と言い換えたってかまわない。私たちは、危険が避けられないまでに迫ってくる前に、そうした気配を察知すること、「危険かもしれない」と予知すること、そうした直観を頼りに生き延びてきたのである。
恐らくそうした直観が、私たちの種としての生存を支えてきたのである。それは現代にも通じる必須の技なのである。「地震がくるかもしれないから家具を固定しよう」、「電話が鳴ったらオレオレサギをまず疑おう」、「暗い夜道の一人歩きは避けよう」、「知らない人から声をかけられたら、まず逃げよう」、「土砂崩れがあるかもしれないから、がけ下に住宅を建てることはやめよう」などなど、・・・。
人は得てして起きないかもしれないこと、起きるはずのないことにも危険を予想して回避しようとする。そしてその予想か外れたとき、その予想は偏見となる。「原発事故、二度あることは三度ある」は人によって偏見になるし、「もし隕石が直撃すれば原子炉も高層ビルも一撃で破壊される」は、恐らく偏見になってしまうだろう。
言葉の通じない、皮膚の色の違う、そして習慣や身なりも違う外国人を恐れるのは、もしくは胡散臭く感じるのは、私たち人間が持つ生き延びてこられたことの証左なのである。その予知や予想が正しいといっているのではない。人間も含む生物がそう作られていることを理解すべきだといいたいのである。
世界中にまたがる難民問題も、つまるところは私たちが否応なく持っている「よそ者」意識からくるものだと思うのである。「よそ者」とは「得たいの知れない者」と同義であり、「得体の知れない者」の危険の程度は「誰も分らない」のである。だから例えそれを偏見だといわれようとも、それが人なのである。その偏見で私たちは生きてきたのである。生き延びてきたのである。
2018.1.20
佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ