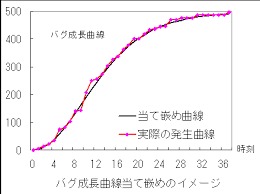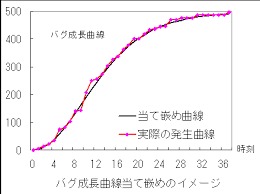数学で習ったのか、それとも社会現象を表す傾向として学んだのか記憶がないけれど、成長曲線という概念をなぜか覚えている。例えば数個の細菌がシャーレなどの中で分裂して増殖する場面を考える。最初は一個が二個、二個が四個などとそれほど気にならないほどの増え方であるにもかかわらず、次第に数万個、数百万個というように、グラフで表すなら垂直に近いほどの増え方の時期を示し、それが過ぎるとあたかも成長が止まったかのように水平状態になってしまう傾向をいう。
つまりは、どんな成長もピークを過ぎると伸び率が止まってしまうような様子を言う。細菌に限らず、ネズミ算と呼ばれる増え方も成長する経済の行く末も、更には戦争の拡大なども、一定の均衡状態でストップしてしまうとの傾向を表す一種の神話である。
それはある意味正しいのかもしれない。それは、成長には資源が必要だからである。無限の資源などありえないことを前提にするなら、成長もまた限界があるとする考えは理解できる。食べ物がなければ、ネズミは子孫を増やすことなどできないからである。
1匹のネズミが月に2匹の子を産み、その子も次のひと月に更に2匹の子を生むとする。つまり、ネズミが月に二倍ずつ増えていくということである。これが続くとすると、仮にその親が死なないとするなら、30世代後にネズミの数は約10億匹になる。そして次の世代には20億匹になるだろう。
だが、20億匹に食べさせていくだけのエサがなければ、不足するエサに対応するネズミはやがて死滅してしまい、そこで増加はストップするだろう。そんなことくらい、誰にだって分る道理である。しかもストップする原因は、エサだけに限るものではない。居住する空間の広狭や温度や湿度などの環境、病気やストレスの有無などにも同様に影響されることになる。
ところで、それが現在の地球の姿であり、人類の現在と将来を示しているように私は思ってしまったのである。つまり、ネズミの例は人間にもそのまま当てはまるのではないかと思っているのである。人は既にあらゆる面で限界にまで到達してしまっており、あとは衰退を待つばかりの状態にあるのではないかということである。
人は必ず進歩するものだと、私たちはこれまで思い込んでいた。進歩することが人間であり、それが正しいあり方なのだと信じてきた。石器時代から始まって現代まで、人は進歩し続けてきた。止まることはあたかも罪であるかのように、私たちは急かされ前のめりになって走ってきた。「産めよ増えよ、地に満てよ」は聖書時代からの私たちに対する哲学であった。
そうした先に今がある。その今は、あたかも垂直の成長期に当たっているかのような現象を示している。それはまさに私の生きてきた時代にそのまま対応しているかのようである。私自身の生活でいうなら、電話もなくテレビもない時代から、宇宙へロケットが飛び出し、スマホが社会を席巻するまでの世界へと激変した。
環境は地球汚染をほしいままにしている。宇宙開発はロケットの残骸や部品などの、デブリと呼ばれるゴミを撒き散らし、核開発はアインシュタインが語った「第三次世界大戦がどのようなものかは知らない。だが第四次世界大戦なら知っている。それは石合戦だ」の予言、つまり石器時代への退行を予感させている。
遺伝子操作は人間のクローンを作ることができるまでになり、人工知能は人との共存から離脱しようとしている。人はどこから来たのか、どこへ行こうとしているのかは、私たちの根源的な問いかけであったはずである。その答を見つけられないまま、人はその疑問そのものを無視しようとしている。そうした傾向は、難民や貧困や戦争などの未解決、人の差別が更に激化し、拡大され、無視され、放置されていることからも、はっきりと見てとることができる。
科学だけが暴走しているのではない。経済も政治も、もっと小さな人と人の触れ合いまでもが暴走している。そんな時代が現在である。そしてそんな暴走は人類だけに見られる現象であることに気づく。人はいつの間にか他者に君臨することに快感を覚えるようになった。勝者になれることの中に快感を味わうようになった。
そしてそうした快感は多数の虐げられる者を生み出し、あてどなき「進歩」という名の暴走に、人はその身を委ねようとしている。
成長曲線の将来は、垂直に近い推移を経て、やがて水平になることを示していた。だが、それは間違った解釈なのかもしれない。水平とは、少なくとも現状維持の継続を意味している。だが現代の人類を見るとき、その将来は水平維持ではなく、むしろ垂直の暴走の後に訪れる「突然の停止」、しかもその停止は平衡維持ではなく、絶滅への急落を示唆しているように思えてならない。
人類は種として、間違った方向へと進化を遂げたのかもしれない。地球には何千万という種が存在するという。そうした数多の種の中でたった一つだけ、「地球にそぐわない種の一つ」として人類は生まれてしまったのかもしれない。それは、地球にも社会や家庭などの小集団にもそぐわない異種であり、絶滅だけが約束された当たり前の種なのかもしれない。
種の発生は偶発的なものであろう。多様な種が環境への適応や順応には無関係に発生し、その中からたまたま適応できた種だけが生き残ってきたのであろう。適者生存は結果論であり、生物は適者になろうとして進化したのではない。首の短いキリンとして発生した種もあっただろうけれど、その生物は適応できない種として絶滅への道をたどったであろうことは明らかである。
だとするなら、ホモサピエンスだけが例外であるはずがない。地球における種の歴史が、絶滅の歴史であることは既に証明されている。生き残ることそのものが、種としての例外なのかもしれない。人類の歴史はたかだか数十万年でしかない。かろうじて絶滅を免れた(僅か数十万年で免れたとは言い切れないとは思うけれど)そんな種が、霊長類とし自称し、世界に君臨する種として自認することなど、どこか不自然である。「発生したばかりの過渡的な一過性の種」、人類をそんな風に理解するほうが私には、とても分りやすいように思っているのである。
2018.2.10
佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ