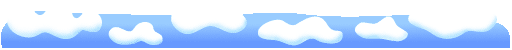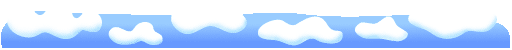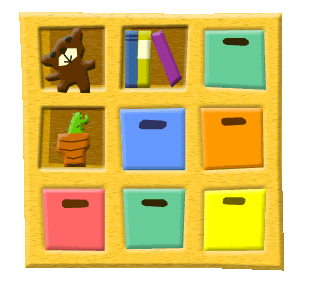親が子供をマンションから突き落としたり、赤ん坊を床に叩きつけたりする。グレた子供は近所に火をつけまわったり、ホームレスは殺しても当然とうそぶく。
殺人も犯罪も、もともと正常な状態ではないのだから、こんな感想をつぶやくのは変なのかも知れないけれど、世の中だんだん理解できないというか、少なくとも私の考えている犯罪の枠組みからはどんどん離れていくような気がしてならない。
その背景は、親の空白にあるのではないか。親と子が離れる原因には離婚や病気や死亡など、様々な場合があるだろう。だが最近の子供の犯罪には、そうした親の事実としての不在ではなく、むしろ居るけれど居ないと言った背景があるような気がしてならない。親が親でなくなってきている、子供は一人か二人なのに昔の子沢山の親よりも関係が希薄になってきている、そんな気がしきりにしてならない。
子供が親や大人、場合によっては社会に逆らうのは当然のことだし、そうした反抗がやがて自立する大人へとつながっていくことなのだと、そうした時代を経験することで子供から大人になってきた(と勝手に思い込んでいる)私としては、「子供の反抗」そのものは、理解できているつもりだつた。
そして時にアウトローとなってグレ始めた子供だって、金八先生や夕焼けに向かって走る熱血先生に、いずれ共感し、納得し、理解して、大人としての涙を流すものだと、無意識に信じていた。
でも最近読んだ「誰がこの子を受け止めるのか」には、遠く遥かにそうした目標を持つことは誤りでないにしても、そんなにたやすく、人はドラマや映画のように、感動して立ち直ってくれるものではないことを思い知らされた。
裏切られても、何度も裏切られても、そして見かけ上すべて拒否されても、そして挫折に負けそうになりながらも子供に向かっていく、いわゆる理解しようとする大人の努力は、時にまるで無意味を積み重ねていくかのように自身の前に立ちふさがる。グレた少年たちの壁は大きく、固く、高く、強い。
そうした少年たちの向かっていく人たちの、時に少年の反感を買い、時に少年を置き去りにし、時には彼らの想いに気づかずに過ごしていく、そんなたくさんの関わりを通じて、少しずつではあるけれど彼らの心が開き、また閉じ、また開きすることが分かる。そして僅かにしろ進んでいくことが分かってくる。
ドラマのように決してある日突然に全身で理解し、親にも先生にも周りの大人や子供にも、だれもが感動の渦に巻き込まれるような大団円の姿には決してなることはない。
「もう、勝手にしろ」、そう言いたくなるような、そしてたぶん私ならそう言ってしまうのではないかと思う状況でも、その人たちは耐え、そして自分を信じている。
「どうして分かってくれないのか」と、時に大人は思うかも知れないけれど、そんな風に大人の思惑通りに動いてくれないのを彼らのせいにするのは誤りだろう。人の心はそんなテレビドラマのように、見ている前で変わるものではない。大きなショック、長く絶え間ない傷つきの時間があって、その心は曲げられる。
嘘をついて学校を休む、仮病もやっぱり本当の病気であろう。訴える内容は虚偽かも知れないけれど、仕事や学校を休みたいと言う意思は、仕事や勉強をするために向けるエネルギーが欠乏したということなのだろう。
こうした子供との付き合いに、筆者は「信じられるから信じるのではなく、信じられないから信じられるようになるためなら、信じるように全力で努力し続けた日々であった」(同p108)と、淡々としかしすさまじい重さで表現している。
そしていつも自分たちが、そうした少年たちと他人であることを自覚している。「職員という環境は、家庭や家族とは似ても似つかないものなのである」(同p118)と理解したうえで立ち向かっているのである。
家庭が壊れる一番の原因は離婚である。結婚は両性の合意でのみ成立する(憲法24条)から、その解除も同様である(民法763条)。だが離婚は一方の親の不在を作ると同時に、残った親も不在になるという二重の不在を作り上げてしまうような気がする。
どんなに考えてみたって、子供がその合意を喜んだり、納得したりするとは考えがたい。それでも離婚は夫と妻だけの意思で決まるのである。離婚は夫婦という共同体の解体だから、構成員である子供にもその解体に伴う不利益や損失や危険を共に負担すべきものなのかも知れない。
だがそれにしても、離婚という決定に参画できないで、不利益だけを受けるというのはやっぱりどこか理不尽である。
彼らのやる気のなさを指摘するのはたやすい。現に意欲の欠如が彼らの特徴でもあるのだから。
しかし、意欲の素地を削いでしまつたのは、だれあろう親だったのではないだろうか。赤ん坊が寝返りを打ったと言っては誉め、這い始め、歩き始めたといっては全き賞賛を与え、字が少し読め、自分の名前を書けた言って天才誕生のように大喜びする、そんな親の無条件な賞賛なくして、人は意欲など湧かないのではないか。
自分の半生を振り返ってみて、少なくとも私は誉められて成長してきたような気がする。時に叱られらたことがエネルギーになったこともないではないが、思い出す多くが、おだてにしろ誉められた記憶であり、そのことが次へのステップ、より大きな賞賛を得ようとする動機付けにつながっていたような気がする。
「親が子を見守る」とは、打算や義務や、こうあるべきと言った教育論から生まれるのではない。もつと根源的な「無批判な愛」みたいなものが源泉になっているものなのではないだろうか。まっすぐに見ているだけで親は親になれるのではないのだろうか。
児童虐待のニュースが少しも珍しくなくなった。親は躾だとうそぶき、そうした子供の瞳からはどんどん光が消えていく。反応しない子供、無感動な子供、そして突然に切れてしまう子供、いったいこれはどうしたことなのだろうか。そうしたことに関わる人が増え、国も自治体も制度を設ける。学校も警察も病院も、児童福祉施設などの多くの機関もこれに対処しようとしている。
それが不必要だというのではない。むしろ必要なのだと思う。親でない者が親子の関係を子供に教えようとしている姿は本当に頭が下がる思いがするけれども、どこか違和感が避けられない。違和感で片付けられる問題でないことは十分承知していながら、どこかで「親はどこへ行ってしまったのだろう」と考え込んでしまう。
これは子供だけの問題なのではない。その子はやがて大人になるのである。親を理解しないまま親になり家族を作っていくのである。
2004.02.15 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ