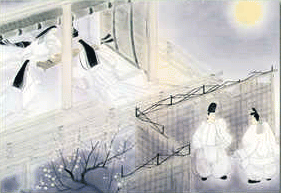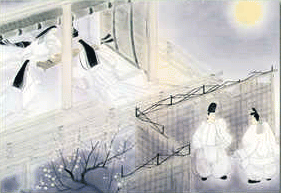紫式部の個人的な好悪なのか、それともその時代の共通の美意識によるものなのかは分からないが、式部の描くこの巻の主人公末摘花の書きぶりは、女が女を書いたものだけに残酷と言ってもいいほどである。
末摘花とは山形などの特産で、かつて口紅や頬紅の原料として有名だった紅花の異称である。末のほうから花を摘みとっていくことからこのように名づけられている。
この時代、女性に名前をつけることや名前で呼ぶことは稀であった。だから末摘花はこの巻の名称であり、同時にこの巻の女主人公の名称にもなっているが、それは紅花を紅鼻にかけた式部特有の皮肉である。
とにかくこのお姫様は鼻が赤い。付き合ってしまったことを後悔するかのように、源氏はこんな歌を詠み、それがそのままこの巻の名称になっている。
なつかしき 色ともなしに 何にこの
末摘花を 袖にふれけむ
(それほど心惹かれる人でもなかったのに、なぜ末摘花のように鼻の赤いあの人に触れてしまったのだろう)
それだけではない。式部はこのお姫様をこんな風に表現するのである。
「この人から美しいところを発見することができたらうれしかろうと源氏の思うのは無理な望みである。・・・はっとした。その次に並はずれなものは鼻だった。・・・象という獣が思われるのである。高く長くて、先のほうが下に垂れた形のそこだけ赤かった。・・・顔は雪以上に白くて青みがあった。額が腫れたように高いのであるが、それでいて下方の長い顔に見えるというのは、全体がよくよく長い顔であることが思われる。痩せぎすなことはかわいそうなくらいで、肩のあたりなどは痛かろうと思われるほど骨が着物を持ち上げていた。」(与謝野晶子訳)。
なにもそこまで言わなくてもと思うほどであるが、式部の末摘花いじめはまだまだ止まるところを知らない。この巻の終わりのほうで、源氏は髪の長い女の絵を描いてその鼻を紅く塗ったり、自分の鼻に紅を塗って「私の鼻がこんなになってしまったらどうしよう」などと幼い紫と遊んだりするのである。
ところで、彼女は亡き常陸親王の娘という設定である。親王とは天皇の子または孫に与えられる身分であるから彼女は高貴の出であるが、既に両親も亡くなっており後ろ盾を持たない生活は貧しく悲惨である。
後ろ盾のない高貴なお姫様がいる・・・・・、夕顔を失って淋しい思いをしている源氏の耳にこんな話が飛び込んでくるところからこの物語は始まる。
琴の名手で髪が長い、そして没落した姫君。この伝聞から想像する女人像は、勝手な妄想と言ってしまえばそれまでだけれどたおやかな美人そのものである。しかも、それと同時に正妻葵の上の弟で、あらゆる場面でライバルとして登場する頭中将も彼女に興味を示し始めたことが、源氏の競争心を一層煽ることになる。
ことは既にゲームと化した。女にしてみれば仕掛けられた恋だけれど、源氏にとってはもう恋を超えた負けられないゲームである。どちらが先に彼女のハートを射止めることができるか、ライバルと交わす手練手管の数々は読者の興味を大きくそそる。
やっと一歩先んじることのできた源氏であるが、その最初の夜に早くも失望してしまう。末摘花には女としての反応が感じられないばかりか、会話も手紙も古臭く、一度そう感じてしまうと、建物も調度品も取り巻く女房たちもことごとくが気に入らなくなってくる。
こうなった以上はせめて顔だけでも見て満足したいと願う源氏であるが、その結果は上述のとおりだったのであり、あまりのことに愕然としてしまう。
さてここから源氏の対応が変わってくる。源氏は「並みの女ならこのままさよならできるのに・・・・」と自嘲しつつも、彼女の生活の一切の面倒を見ることにするのである。
これは一面、気まぐれではあるけれども、源氏の持つ優しさの表れと言えるかも知れない。この数年後、源氏は須磨へ流されて不遇な境遇を迎えることとなり、その間彼女は忘れられてしまうのであるが、復帰後は偶然の機会からではあるが改めて彼女の後ろ盾となり、きちんとした面倒を見ることになるのである。
末摘花は源氏物語の中では、一種の残酷な滑稽譚として登場するだけで、その後も時々顔を出すけれども物語の主要部分に名を連ねることはない。
ただ、それにしては彼女の出番は、他の多くの女性に比べて多いような気がする。
「蓬生」(よもぎう)の巻になると、末摘花の描写は容姿・容貌から離れ、侮蔑的な表現も控えられてくる。既に源氏は須磨へ流されていて、彼女のことを忘れている。彼女の叔母はかつての常陸宮から侮辱されたことを根に持ち、姪である彼女に「もう源氏はお前のところには来ない、私の召使になれ」などと意地悪く接するのであるが、彼女はいつか源氏が京へ戻ってきて自分のことを思い出すと信じ、叔母の雑言にひたすら耐えている。
そして別離から4年、花散里を訪ねる途中に源氏は荒れ果てた、しかし見覚えのある常陸宮の屋敷を見つけるのである。彼女のことは忘れていたにもかかわらず、末摘花は宮家の姫としての誇りを守り抜き、自分を信じて待っていてくれた。そのことに源氏は自らを恥じるとともに感動すら覚えるのである。やがて彼女は源氏に引き取られ、更に二年後には二条院東院に移り住む。
このあたりはまるでシンデレラ物語りを読むようである。
それでも生来の古臭さは相変わらずで、歌の言葉遣いにも筆跡にも、更には使者への引き出物の選択にも源氏は閉口するばかりである(「玉鬘」(たまかずら))。
既に彼女の長い髪に白髪がまざりはじめるようになっても、相変わらず衣服のセンスは悪いし、話し声も震えている上に冗談も通じないなど、垢抜けしない状態が続いている(「初音」)。
また玉鬘の「裳着(もぎ)の儀式」(女子の成人式)に際しても、勝手に贈り物を送りつけるなど、その出過ぎた態度に源氏は顔を赤くするばかりである(「行幸」みゆき))。
そうは言っても、彼女に悪気はなく、宮家の姫として誠心誠意自分の気持ちを伝えようとしているのだということは源氏にも分かっている。
だから小馬鹿にしている感じはあるものの、迷惑であるとかいらいらするというのとは違って、ゆとりある鷹揚な接し方が感じられる。もしかすると源氏にとって末摘花は気の置けない女、気遣いをしなくてもいい女であり、しかも自分に全面的に頼り切っている女として、無遠慮にそして無防備に過ごせる場所として考えていたのではないだろうか。
「若菜・上」で、病床に伏している末摘花を忙しさに紛れて見舞いにも行けないと嘆く源氏の言葉を最後に、以後彼女は物語から淋しく消えていく。
彼女の一生とはなんだったのだろうか。確かに不美人で教養に欠ける面が多かったかも知れない。しかし、宮家としての誇りを保ちつつ、何も求めない女であった。ひたすら待つだけの女であった。しかも待つことに何の疑問もためらいも感じることのない女であった。
源氏の生涯は、逆に言うならば女に翻弄された生涯でもあった。そうした中で、権力闘争にも無関係で嫉妬さえもすることのなかった、ただ待つだけの女の存在は、どんなにか貴重で心休まる場所ではなかったかと思うのである。
出会いの時の源氏は18歳、そして「若菜・上」の源氏は41歳である。須磨へ流されていた期間のギャップはあるものの、源氏は23年もの付き合いを彼女と続けているのである。
彼女と源氏の間に男女の関係は滅多になかったとされている(「蓬生」)。末摘花が源氏41歳の時に病気になったことは前にも触れたが、そのまま亡くなってしまったのかどうか、それは分からない。それでも物語りに表われる限り、源氏は最後まで彼女のことを気遣っている。
恋と言えども身分から離れることはできず、嫉妬や裏切りや権力闘争、更には男の身勝手の中で翻弄され続けるのが常であった。そうした中で多くの女が「出家すること」に己の救いを見出そうとしていた。最も幸福な女だと思われている紫の上にしたところで例外ではなかった。
そうした数々の女たちの中でこの末摘花は、源氏に守られているというそのことだけに満足し、宮家の姫としての誇りを貫き通すことのできたとても幸せな女だったのではないだろうか。
紫式部も、そしてその当時の多くの読者も、彼女を単に不美人の可哀想な女ではなく、誇り高く生き抜いた幸せな女として見ていたのではないだろうか。だからこそ彼女は、源氏物語の中で繰り返し繰り返し語られ続け、その人気を保ってきたのではないのだろうか。
2004.09.13 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ