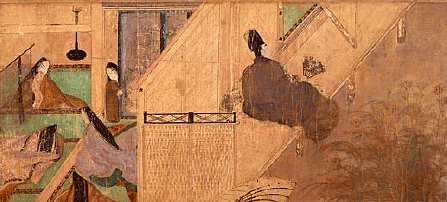浮 舟(うきふね)
源氏物語は源氏の誕生からその死、そしてその子の薫(かおる)、更には孫の匂宮(におうのみや)へと続く五十四帖、80年にも及ぶ壮大なドラマであり、しかも概ね時系列で語られているから、興に任せてのつまみ読みも楽しいけれど、基本的には順番に読んでいかないと筋書きが理解できないということにもなりかねない。
しかも登場人物が男は官位で呼ばれることが多く出世していくたびに名称が変わること、女は時に「誰々の娘」と呼ばれ、あるいは住んでいる部屋や歌、風景、近くの花の名などで呼称されたりして、その時々で名前が変わるなど、系図を頭にいれ、人物を追いかけ、男女の関係を理解しながら読み通すのはけっこう大変である。
時には第一巻の桐壺だけでギブアップしてしまうこともあるし、せいぜい夕顔(三巻)、若紫(五巻)、紫の上と結婚する葵(九巻)くらいまで読み続けて卒業したことにしてしまうこともある。
ところで浮舟は源氏物語最後のヒロインであり、源氏死後の薫(実は源氏の正妻女三宮と柏木との不倫の子)と匂宮(源氏の娘である明石中宮と今上帝との子、つまり源氏の孫)との三角関係の物語であるが、この物語は宇治十帖と呼ばれる源氏物語最後のグループに位置しているから、ここまで読み通すのはかなりの根気が必要となるかも知れない。
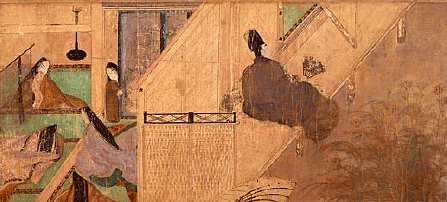
秋の冷たい雨がそぼ降り、八重葎の庭も闇に包まれた頃、三条の隠れ家に住む浮舟を訪ねる薫(東屋)
浮舟はこの薫と匂宮の二人に同時に愛された女である。生まれながらに芳香を体臭として持つ薫と彼にライバル心を燃やし薫物(たきもの)で対抗する匂宮、そんな二人の男に翻弄される女の物語は、現代にもそのまま続く古くて新しい物語でもある。
この物語を理解するためには、この三人の出会いの前に、源氏には八宮(はちのみや)という異母弟がおり、その八宮には二人の娘がいて、薫がその娘の後見になるように八宮から頼まれるという前提を知つておく必要がある。
八宮は源氏が須磨に流されたとき、反源氏派としての右大臣勢力に担がれたことから、その後の源氏隆盛のもとで疎まれ、都会を離れて宇治に住み不遇な生活を送っているが、深く仏道に帰依している。こうした世間から少し離れた八宮の生活に薫は純粋なものを感じ、彼のもとへ熱心に通って教えを乞うている。
その背景には、誰から聞いたというのでないものの、薫は自分が源氏の子ではないのではないかという疑いを拭い去ることができず、世上の人気とは別に、内心では密かに出家を考えていたことがあげられよう。
ところでこの八宮の二人の娘(大君・おおいぎみ、中の君・なかのきみ)は共に美しく、特に大君の美しさは薫の出家の考えなど、あっさりと吹き飛ばしてしまうのに十分であった。やがて八宮はこの二人の娘の将来を薫に託して(つまり結婚して後ろ盾になってほしいと望み)他界する。薫の心はどんどん大君に向かっていくが、大君は父亡き後の自分を世捨人のように扱い、むしろ妹を薫の妻にさせようとする。思いを断ち切れない薫は、中の君を匂宮と結婚させることで、大君の心が自分になびくのをじつと待っている。
この辺の大君に対する薫の感情は非常に屈折している。実は薫は機会を捉えて大君の寝室へ忍んで行くのであるが、結局彼女の気持ちを尊重する余り、添い寝をするだけで一線を越えるまでにはいたらないのである(橋姫)。
また、二度目のチャンスの時には、大君は中の君を残して隠れてしまう。大君としてはそうすることで薫と中の君を結び付けようと考えたのであるが、ここでも薫は大君への愛の証を示すため、中の君と一線を越えようとはしない。
しかも大君は最後まで薫を受け入れることなく、むしろ中の君と結婚してくれない薫を恨みつつ、その心労で誰とも結婚しないまま死んで行くのである。
薫の嘆きは大きいが、こうした嘆きの最中に、なんと大君が生きているのかと見紛うほど彼女にそっくりの浮舟が登場する(宿木)。浮舟は八宮の腹違いの子、つまり、大君、中の君とは母違いの妹である。
ところで自らが匂宮との結婚を画策したにもかかわらず、まだ浮舟の存在を知らない薫は、大君亡き後、今度は未練がましく中の君に言い寄る。色々事情はあるにせよ、中の君にしてみれば薫は姉を死なせた張本人である。匂宮の妻でもあり、薫を遠ざけたいと願う中の君は、浮舟の存在を知らせることで薫の気持ちをそちらへ向けようと考える。大君を思い続けている薫の気持ちがこの浮舟に向かうのにそう時間はかからなかった。
浮舟は少し前、縁談が壊れたことによる心労を癒すため中の君に預けられているが、中の君を訪ねてきた匂宮に発見されてしまう。しかも匂宮は邸内に美しい女がいるのを見て、いきなり抱きすくめる。この時は乳母の機転でことなきを得るのであるが、この時から匂宮にとって浮舟は「惜しいところで逃げられた女」になったのである(東屋)。
こうして浮舟は二人の男と出会うことになるが、薫と匂宮とはライバルとしての設定のほかに、性格的にもまったく異なる人物として描かれている。
薫は、前述した通り我が身の出生の秘密を密かに感じており、そのことが彼の性格を内向的なものにしている。つまり薫は内省的、情緒的であり、現世から逃れて出家を考える、いわば思索の人である。
これに対し匂宮は、薫に対抗して行動するような動的な人物である。自分の出生にも、生い立ちにも、更には美貌にも才能にも自信を持ち、心の赴くままに行動することが正義であると確信している信念の人である。美しい女を征服することも含めて、自分の望むように生きることが彼の自信であり、人生そのものである。
浮舟の悲劇は、こうした余りにも対照的で魅力的な男に同時に愛されたことである。自分を深く理解し一生を託するに足る人物、そして精神的に頼れる男として薫を選ぶか、それとも肉体的な欲望をまっすぐにぶつけてくる匂宮を選ぶべきなのか。いや、浮舟の本当の悲劇は、どちらをも選べなかったことにあるといえよう。浮舟が自分の気持ちをきちんと整理していずれかを選んで決心したするならば、これから起こる悲劇は避けられたはずである。
浮舟は二人の男を同時に愛してしまう。それを身勝手と言うのは当たらないだろう。自らの意志を示すことの難しいこの時代の女の立場を考えるとき、薫の深い思いやりに感謝し、上品で教養ある姿を愛しつつ、同時に男として彼女に始めて迫ってきた匂宮の魅力にも逆らえないまま翻弄されて行く、その姿は余りにも哀れである。
匂宮は積極的である。これに呼応する薫の行動も、彼の性格からは予想もつかないほどに積極的になる。それは愛なのか、それとも匂宮への対抗意識なのか、このない交ぜになった男二人の感情のもつれは、結局浮舟を追い詰めていく。
薫は、匂宮から逃れて中の君の屋敷から三条の隠れ家に移り住んでいた浮舟のもとへ中の君の手引で通っていたが、宇治の御殿へ連れて行き愛人として住まわせることにする。宇治を選んだのは、そこがかつて大君の住んでいた場所であり、大君との見果てぬ夢を浮舟の姿を借りて再現しようとしたのかも知れない。
この後は二人による浮舟の壮烈な奪い合いとなる。宇治と京は遠い。政務に追われる薫の訪れが疎遠になる隙を突いて、匂宮はあろうことか薫を装って宇治の館へ入り込み浮舟と一夜を共にし、そのまま数日居続けるのである。
突然の悲劇に嘆く彼女であるが、やがて浮舟の心と身体は別々の男を求めるようになる。静かで頼りになる薫を心は従うべきだと教えている。しかし、それでもまっすぐにぶつけてくる匂宮のこの激しい情熱にどうして抗えようか。そして匂宮の心も、いつしか遊びの気持ちを離れて彼女を独占したいと思うようになっていく。
たちばなの小島は色も変わらじを
この浮舟ぞゆくえ知られぬ
冬二月、忍んできた匂宮と小船で隠れ家へ向かう時の、行方定めぬ我が身のはかなさとその恋に身を投じたわななきを読んだ浮舟の歌である。彼女が浮舟と呼ばれるのはこの歌からきている。
やがて二人の仲は薫の知るところとなる。薫は怒りつつも、しかし彼女を諦めようとはしない。彼女を捨てることは浮船が匂宮の女になることを認めることであり、そんなことには耐えられないと考えるのである。
そして薫は浮舟を守るため、京の屋敷へ引き取ろうとする。それを知り、その前に彼女を奪取しようとはかる匂宮、その日は刻々と近づき、決断を迫られる浮舟。
この辺の女心の描き方は、私達にも非常に分かりやすい。常識的には、匂宮と逃げることは薫に対する裏切りであり、将来を考える上でも恐ろしいことである。しかも彼女は薫を深く愛しているのである。
一方、匂宮の愛は肉体への愛である。数多の女を渡り歩くプレイボーイにとって、自分への愛はすぐにでも醒めるかりそめの愛かも知れない。それならそれでもいいと、身体は匂宮を待ち続けている。
結局彼女は、流れの速い宇治川に身を投げるという形で二人の男への愛を清算しようと考える。
雨の日、彼女の失踪に気づいて館は大騒ぎとなるが、結局は宇治川へ身投げをしたのだろうということで、遺骸のないまま彼女の葬儀が行われ、薫も匂宮もそれぞれに深く嘆き哀しむ。
ここで物語を終えても特に不自然ではない。しかし、紫式部はこんな平凡な終わらせ方をするような作家ではなかったのである。
彼女は死んではいなかった。宇治川の対岸で記憶を失なった女を、横川(よかわ)の僧都が助けるのである。記憶喪失は徐々に直っていくが、彼女はそれを周囲の人々に知らせようとはしない。そしてその美貌から寄せられる結婚話も、戻りかけている過ぎし日の苦悩の前にはむしろ困惑するばかりである。彼女は突然出家を決意する。
そして後日談。こうした女の噂を聞いた薫は、もしや浮船が生きているのではないかとの疑念を抱き、彼女の弟に託して浮舟に文を渡そうとする。しかし出家してしまった彼女は昔を振り返ろうともせずその文を見ることすらしない。それを聞いた薫は、逆に出家は偽りであり浮舟は誰か別の男の愛人になっているのではないだろうかと疑う(夢浮橋)。
いかにも薫らしい、煮え切らない下司の勘ぐりではある。そして、源氏物語全五十四帖はこの「勘ぐり」で唐突に終わるのである。未完なのか、紫式部はこの結末で良しとしたのか、諸説あるけれど、ともあれ浮舟は自らの意志で出家を遂げ、男に翻弄されることのない自らの世界を確立することができたのである。
これを女性の自立と呼ぶには、今の時代感覚ではおこがましいかも知れないけれど、少なくともこの時代に生きた女としては、精一杯の自立であったということができるのではないだろうか。
一人の女の哀しい生き様が千年の時を超えて共感を呼ぶ。男と女の物語はいつの世も答えのない迷路の中を漂っているということなのだろうか。
2003.11.19 佐々木利夫
|