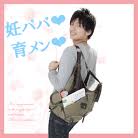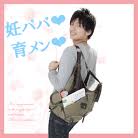今年の流行語になりそうな勢いを見せている言葉の中に「イクメン」がある。若い父親の子育てを意味する言葉で「育メン」の意味である。男も共に子育てに参画すべきだというメッセージがこのところ社会の中に広まってきて、それなりの地位を得てきていることがこうした造語が流行する背景にあるのだろう。
夫婦で共に育児をすることについて私は反対するつもりはない。子供の成長にとっても、夫婦による子育ては望ましいスタイルであろうことを理解し納得もしている。ただ、こうした「夫も共に育児」の背景にあるのは男女共同参画のような考え方ではなく、どちらかと言うと「育児は大変だ」のような女の悲鳴だけのように思えるのが、どこか引っかかるのである。
確かに育児は大変である。物言わぬ赤ん坊に、いかに我が子であるにしても二十四時間拘束されることの大変さを理解できないではない。夜昼問わずに泣き止まぬ我が子、痛いのか腹が減ったのかオムツが汚れているのかそれとも単に泣きたいからだけなのか、そんな子に付き合っていく大変さが分からないではない。
そんな大変さを「昔の人はちゃんとやっていた」だけで済ますことはできないだろう。それはそうなんだけれど、それでも私は「昔のお母さんはそんな赤ん坊にちゃんと付き合っていた」のだと、どこかで言いたいような気がしているのである。しかも子育ては今でこそ一人か二人だけれど、私の生まれた頃の子供の数は、私の兄弟でも私を含めて5人、中学の同級生には続柄9女というつわものがいたのを記憶しているくらいだから今とは比較にならないくらい多かった。そのことはそうした子供の数だけ母親は子供を育てたということでもある。
そうした時代を経て今の私たちがいる。そして今のお母さんが「子育ては大変だ」と訴え、その大変さが嵩じて幼児虐待やネグレクト(育児放棄)などに結びつく例もあると言われている。さてここで考えられるのは、少なくとも「赤ちゃん側の変化」ではないと言うことである。昔の赤ん坊と今の赤ん坊で、育ててもらう相手に対して何らかの対応の変化を示すようになってきたとは考えられない。昔も今も、赤ん坊はひたすら泣くだけだったと思うのである。お母さんを困らせようだとか、泣き声のボリュームを1段上げようになどと考えてはいないと思うのである。つまりは育児の大変さの拡大は、もし拡大があるのだとすれば「同じ赤ん坊に対する母親の気持ちの変化」であるに過ぎないのではないかと思うのである。
誤解しないでもらいたいが、だからと言って育児は昔どおり母親だけに任せるべきだと言っているのではない。むしろ私は現代の母親の意識なり立ち位置が、昔よりも相対的に「大変さ」の方向へとシフトしてしまっているのではないかと言いたいのである。
昔の夫婦の姿を本来あるべきスタイルだというのではないけれど、男が狩りをして家族の食料を確保し女が出産と育児を分担することは、少なくとも人が種として生き延びていくための手段として自ら選んだ手法だったのではないかということである。だからと言って育児の分野に男が入り込むことを否定するものではない。しかし、男の役割を変えずに残したまま、それを超えて女の役割へと侵入を求めるのは女のエゴになっているのではないかと思えるのである。
そうした意識の変化は単に男女共同参画時代へと人類が進化していったと言うのではなく、種としての人類の起源と繁栄を維持してきた個体としての「人類の進化」とどこか矛盾するように思えるのである。
もちろん一つの形として「主夫」の存在を否定するつもりはない。育児を夫が分担し、狩りつまり生活の資を将来とも妻が分担するような夫婦の形を知らないではないし、そうしたスタイルを認めることにやぶさかではない。
ただ、現在色々な形で要求されている「育メン」はそうではないように思える。つまり、妻が夫の育児への参入を望むことを単に妻からの要求だけではなく社会そのものの要求なのだと位置づけるなら、同時に妻もまた夫の狩り(仕事や住宅ローンや育児や教育のための費用の捻出などなど)に対する相応の分担を課してもいいのではないかと思うからである。
「育児は大変だから夫も共同すべきだ」が時代の要求として主張されるのならば、同じように「家族の維持費は大変だから妻も共同すべきだ」もまた並存していいのではないだろうかと思うのである。
だとすれば育メンへの意識の流れは、そうした「育児の大変さの緩和・大変さの均等分担」と言った母親の負担軽減とは別の視点から捉えていくべきではないだろうか。
つい最近「孤育ての国」と題する新聞の特集記事を読んだ(2010.11.23、朝日新聞、オピニオン)。そこには3人の女性による評論が掲載されており、それぞれの立場の違いが見て取れて興味深かった。
「
・・・母親がだめになったのではなく、(頼れる親族の減少や長時間労働による夫の家事からの離脱などによる)人口学的条件と社会的インフラの問題なのです」(落合恵美子「母親の変質より社会の問題」)としているの意見がある一方で、もうひとりの投稿者は「
自分が出産するまで、子どもは3歳くらいまでハイハイしているものかと思っていました。妊娠した時は摂食障害気味だったし、薬と酒とたばこで生き延びているような生活だったので、子どものいる自分というものに違和感があって・・・」(金原ひとみ、芥川賞受賞作家、「1対1はどんづまりの関係」)と話しているのは余りにも考え方に違いがあり過ぎて思わず絶句してしまった。
また別のひとりは、「
・・・今の母親たちは、出産するまで自分の時間が潤沢にあった世代です。・・・まじめで挫折を知らない人ほど苦労してしまうようです。・・・情報を応用して自分の子どもにあてはめる力が欠けている、と感じます」(大日向雅美、子育て支援NPO代表理事、「完璧目指さず育つ力信じて」)と話していて、どこか正論を述べているだけで欲しい答えにはどこか届いていないように思えた。
まあそれぞれに理解できる部分を持ってはいるのだが、いわゆる「子育てママの孤立感」と「育メンに対する社会的な承認」みたいな意識とがどこかで咬み合っていないように思えたのである。
これと同時に発表した「
就職超氷河期」と重複するかも知れないけれど、男がどこか頼りなく思えるのは私の偏見なのだろうか。「黙って俺に着いて来い」だけが男としての望ましいスタイルだとは思わないけれど、育メンだとか草食系男子などの言葉の行き交う現代は、少なくとも私にしてみると「男よしっかりせい」と尻を叩きたくなる時代であるように思えてならない。
2010.12.3 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ