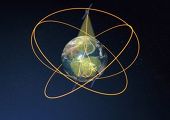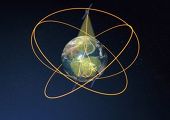一ヶ月ほど前(2010.9.11)、H-ⅡAロケット18号機で打ち上げられた日本の人工衛星はその名を「みちびき」と呼ばれている。カーナビやGPS機能のついた携帯の位置情報の精度を高めるための衛星だそうで、これまでのアメリカの衛星を使っての情報では高層ビルなどで電波が影響され不正確になりがちだったのを補正するためのものらしい。
その打ち上げに際してカーナビなどの開発に係わる企業などを取上げたテレビのニュースで、タイトルのような「これで間違うことが少なくなった」とのコメントがあった。位置情報の精度が誤差1メートル程度にまで縮まるようなのである。このロケット打ち上げそのものに私は何の異論もない。車も持たず、携帯電話とも無縁の生活をしている我が身にとって、この打ち上げによるメリットはほとんどないように思えるが、それでも社会がより便利、より正確な方向へと進んでいくのは現代では当然のことなのかも知れない。精度の高まりはそれだけ利用者の利便性を高めることでもあり、そうした利便性は間接的であるにしろ無関係とうそぶいている者にも及ぶだろうからである。
ところで自宅にしろ事務所にしろ、はたまた通勤で歩いている途中にしろ私の位置は常に自分の目で確認できるのだから、わざわざマシンを使ってまで確かめるような実益などまるでない。また見知らぬ土地への旅行を計画しているわけでもないから、私の位置情報を客観的に知る必要性などもまるでない。にもかかわらず私には、どこかでカーナビみたいなものを持ってみたいような気持ちがこれまでも時々浮かんできたような気がしている。だからこうした「みちびき」のニュースにも、実益とは別になんとなく興味が惹かれたのは事実である。
ただこの人工衛星打ち上げの目的とは丸っきり無関係なのだが、「間違うことの少なくなる社会」みたいなコメントを聞いていささか気になったのである。
それは人はエラーから学び、エラーをバネとして自らを高めてきたのではなかったかと思ったからである。試行錯誤や挫折なども含めて失敗を知らない社会と言うのは、見かけは上平穏かも知れないけれど同時にちょっとした風にも倒されてしまうような脆さを持っているのと同じではないだろうかと思えたからである。
現代がマニュアル社会だと言われたり、女性に興味を示さないいわゆる植物系男子などと呼ばれる存在が話題になっているのも、いわば失敗を恐れる社会や個人の増加がそれを後押ししているからではないだろうか。
しかもそうした傾向は、若者そのものがマニュアルを求め、マニュアルに書かれていないことがそのまま行為者の失敗や責任の免責や言い訳の手段にまで拡大されるようになってきている。与えてくれることが当然となり、自ら手順を見つけたり作り出したりすることが、仕事に対する発想そのものの中から消えていっているような気がする。
そうした傾向の背景には、カーナビのように精密な道しるべを与え続けそれに無批判に従わせることで効率的で即戦力に対応する若者を育てようとした企業や社会の存在があるのかも知れない。たからそうした若者の傾向を、若者だけの責任として押し付けるのは無責任すぎるかも知れない。そして現代の若者を一くくりにして「マニュアル人間」へと総括してしまうのもまた誤りであろう。
だが少なくとも私には現代の若者が、努力型とマニュアル型にあまりにも二極分化されているように思えてならない。試行錯誤にしろ自ら努力しようとしない若者が増えているのでマニュアルを作って訓練しようとしているのか、それとも従業員がマニュアルに従うことで雇う側が満足してしまい逆にマニュアルに反するような自主性そのものを封殺してしまうような組織のあり方に問題があるのか、その辺のことは必ずしも私には理解できていない。
効率化を高めることが企業戦略(もしかしたら単純な利益確保)の重要な要素になり、遠回りや無駄の排除が金科玉条になってきた。使われる者もそれに呼応するように、最短距離を走ることだけに目的を見出すようになってきた。そうした傾向はどこか間違っていると感じながらも、私にはどうすればいいかが見つからないでいる。
こうした私の思いはつい二週間ほど前にここへ書いたエッセイ(別稿「
努力は報われる」参照)と軌を一にするのかも知れないが、目先の楽しみにばかり目が行って、苦労することや我慢することをマイナスのイメージとして捉えがちな風潮がどうにも気になって仕方がない。
それとももしかしたらそうした「目先の楽しみ」は天に唾するようなもので、いずれ我が身につけが回ってくるなどと考えているのは「努力」することに余りにも過大な価値を見出そうとしてきた私たち古い世代の他愛無い夢物語にしか過ぎないのだろうか。現代は既にそうした努力の時代からは遥か遠ざかり、努力することと将来の楽しみや成功とはなんのつながりもない社会になってしまったのだろうか。今楽しむことが将来の報復というか楽しみの喪失にはつながらず、先憂と後楽とが切断されているのなら先楽も後楽もともに味わう方がいいと、そんな時代になってしまったのだろうか。今の苦労が将来の楽しみにつながる保証がないのなら、今の苦労と将来の苦労とが連続することだってあり得ることになる。
だとするなら楽しめるうちに楽しもうと考えるのは当然のことかも知れない。現代はそこまで殺伐化してしまったのだろうか。「夢などない」のが現実で、「夢がある」と考えるのはかつての若者だった私たちの古びた幻想にしか過ぎないのだろうか。
こんな思いは人工衛星みちびきの成功とは何の関係もない。ただ間違いの少ない社会への願望は、どこかで社会のマニュアル化、人生のマニュアル化を示唆しているような、そんな思いを抱かせたのである。
2010.10.21 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ