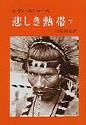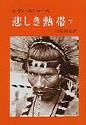こんなタイトルを思いついたのは、年末から正月かけて読んだ「悲しき熱帯」(レヴィ・ストロース著、川田順造訳、中央公論社、1977年10月刊)に触発されたからである。この本に触れるきっかけとなったのは、朝日新聞の天声人語('09.11.30)に彼の言葉として
「世界は人間なしに始まったし、人間なしにおわるだろう」が引用されていたからである。
この引用文に類似した思いは私自身がかねてから抱いていたことでもあり(別稿「
地球の悲鳴」参照)、どちらかと言うと筆者の思いに共感を抱いたからであった。読み始めて分かったのだが、筆者がこの著作を表したのは1955年パリだとされているから1940年生まれの私にとって15歳の時ではあるが、翻訳されたのは先に掲げたように1977年である。とは言っても私はこの著者の名を知ったのは、この新聞記事の引用が始めてだったから、仮にこの著書名を図書館で見つけたとしても自ら手にすることはなかっただろう。
ところがこの本を図書館の閲覧予約ネットで手にして間もなく、彼の死を悼む記事が新聞に載った(「惜別」、朝日新聞、’09.12.13、構造主義の父 クロード・レビストロースさん」、寄稿者 国末憲人)。その記事で彼が昨年の10月30日に亡くなったこと、そして文化人類学のみならず、
「現代思想史に刻んだ足跡の深さは、改めて振り返るまでもない。・・・地質学、音楽、絵画から日本の職人技術にまで至る関心の広さ、主著『悲しき熱帯』は文学としても高い評価を得た。」(上記「惜別」から)と評されるまでの巨人だったことを知ったのである。
ところがいくら読み進めていっても、この本を手にするきっかけになった肝心の引用文が発見できないのである。僅か数十文字のフレーズである。上下二冊、トータル700ページに近い大作の中からこの文字列を探すのは、パソコンなどに入ってるのであれば文字列検索などで容易かも知れないが、読みながら探すのは物理的にはなかなか困難である。それでも気をつけながら読み進めていったのだし、それらしき雰囲気のあるわうな箇所では特に注意していたのだから見逃すはずなどないとも思う。そして大晦日が過ぎ、全九章の著作の第八章も終わろうとするところまで読み進めたのに、まだこのフレーズを発見することができなかったのである。
論文などでの引用であれば引用した著作物の書名や出版社、更には掲載ページなどを記すのは当然のことだし、私もこれまで作成した論文にはもとより、こうして毎週のように書いているエッセイにだって可能な限り原典を表示するように努めている。だが天声人語は警句や俳句などの引用が比較的多いにもかかわらず、引用した著書などの出版先や掲載ページを表示することはほとんどない。
もしかしたら気づかないまま読み過ごしてしまったのかも知れない、ふとそんな思いに駆られる。もしそうなら恐らく手遅れである。これだけの大作をもう一度読み返すことほどのエネルギーは残っていないし、仮にそのために読み返したところで僅か数十文字のフレーズを目で探すことなど不可能なような気がしてくる。
それでもう一度、この文章を引用した天声人語の切抜きを読み直してみることにした。それはこんな文章であった。
「・・・人類学の泰斗、フランスのレビストロースさんが100歳で他界した。名著『悲しき熱帯』を翻訳した東京外大名誉教授の川田順造さん(75)は『先生の言葉で心にしみているのは”世界は人間なしに始まったし、人間なしにおわるだろう”という一節です。・・・』
読み返してみて分かったのは、どうも天声人語の作者はこの一文が「悲しき熱帯」からの引用だとは断言していないのではないだろうかと言うことであった。確かにレヴィ・ストロースの発した言葉であることに違いはないだろうけれど、この天声人語に書かれた文章からではその言葉が著者と訳者との会話の中で出てきたのか、それとも訳者が他に訳した(もしくは原書で読んだ)他の著作の中で書かれた言葉だったのかは断定できないことに気づいたのである。天声人語の作者はレビストロスの代表作として「悲しき熱帯」を挙げているだけにしか過ぎないのではないかと言うことであり、翻訳者は単にレビストロースの発した様々な言葉の中での「心にしみている言葉」としてこのフレーズを紹介しているだけにしか過ぎないのではないかと言うことである。つまり「悲しき熱帯」と「この言葉」との直接的な結びつきはないのではないかと思ったのである。
ところでこの著作は12月の中頃から読み始めたこと、このフレーズが私の思いと共通していたことなどもあって、実は自作の年賀状に「このフレーズに惹かれてこの本を読んでいる」として使わせてもらっていたのである。だから、もしこの一文が「悲しき熱帯」の中に含まれていないと言うことになってしまうと、私は年賀状を出した多くの人に対して結果的に嘘をついたことになってしまうのである。
図書館からの貸出期間は2週間であるが、他に申込者がいなければ一度だけ延長することができる。幸い年末年始は休館になっていることもあって延長期限は年明けになった。そして元旦を迎えた。だが今晩は娘夫婦に孫も集まっての新年会であり、孫はそのまま数日泊まっていくことになっている。昼間は孫と遊び夕食には酒が入るであろう正月の私を思い浮かべると、数日間はこの本を手にする機会など遠くなってしまうような気がする。場合によっては数ページを残したまま三度目の再借り入れが認められない状態でこの本の返却期限が来てしまうかも知れない。
残り数十ページである。年末から元旦にかけ、足掛け2年がかりで一冊を読み終えるというスタイルもそれほど悪くはない。それで元旦朝のお神酒を少なめにして最後の九章へと読み進める。先に書いたように、このフレーズがこの本に含まれていないのではないかとの思いは既に私の中で確定しかかっており、それよりは読了することのほうに力が入っている。
そして元旦の午後、突然にそのフレーズを発見したのである。なんとこの言葉はこの本の第九章、つまり最終章の、それも末尾359ページの僅か4ページ前と言う場所に突如としてその姿を現したのであった。それは「この本の中には収録されていないだろう」と諦めかけていた私にとってみれば、曙光とも言えるような突然の出会いであった。
「世界は人間なしに始まったし、人間なしに終るだろう。制度、風俗、慣習など、それらの目録を作り、それらを理解すべく私が自分の人生を過ごして来たものは、一つの創造の束の間の開花であり、それらのものは、この創造との関係において人類がそこで自分の役割を演じることを可能にするという意味を除いては、恐らく何の意味ももってはいない」(「悲しき熱帯 下」P356)。
「人間の精神が創り出したものについて言えば、それらの意味は、人間精神との関りにおいてしか存在せず、従って人間の精神が姿を消すと同時に無秩序のうちに溶け込んでしまうであろう」(同書P357)。
やっと発見できた嬉しさに、私はしばらくこの言葉を反復して読み返していた。そして間もなく私はこの壮大な著書の全ページを閉じることができた。平成22年元旦、どこまで理解できたか心もとない限りだし、生半可な理解のせいか反発を覚えるような記述にもいくつか出合ったけれど、アマゾンの奥地のまさに人跡未踏とも言える地域の小数民族と著者との出会いを通じた「人間とはなにか」、「人類とは何か」、「人はどこから来てどこへ行こうとしているのか」などの思いの片鱗に、私も少しは触れることができたように思えたのであった。
かくして私の平成22年は僅か数十文字の文字列の検索とその発見で始まったのである。そしてその時に思ったのは、仮にこの文字列が見つからなかったとしても、決してこんな重たい内容の本を二度と読み返すような気にはならないだろうと言うことであった。そして発見できた嬉しさと同時に、なんだか肩の荷を降ろしたようにとても「ホッ」としたのである。それはいわゆる読書とはどこか違った感慨であった。
夕方が近づき娘夫婦や孫たちが集まってきて、いつもなら夫婦二人の生活が突然にあわただしくなった。娘二人に任せたおせち料理が並び缶ビールが開けられ、珍しい焼酎や日本酒がふんだんに行き交う宴会になった。私たち夫婦も含め集まったそれぞれが平穏で平和な2009年であったことを祝い、私は酔った。それはどこかで「人間とは何か」が少し理解できたかのような錯覚を含む、そんな嬉しさでもあった。
2010.1.08 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ