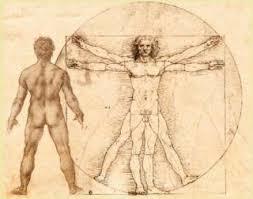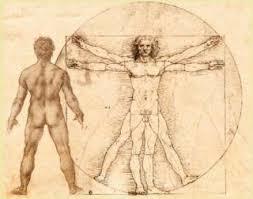連続とは全体が切れ目なくつながっていて、本体を損なわずに切断できないことを意味している。例えば数列は常に連続である。数列を小数点以下の任意の位置で切断したとき、そこが常に隣の数値とつながっていると言うことである。つまり逆に不連続とはそこに切断できる境界があって、切っても血が出ないということである。
だが想像だけにしろ、その数値に接着する更に細かな数値が存在するであろうことは誰にでも分る。0.001やもっと小さなある数値が「ここが最小単位の境目である」というような点が存在しないことは考えるまでもなくすぐ分る。どんな数値にもその数値の更に10分の1、100分の1、133分の1などと言った値をいくらでも考えることができ、切断面などないからてある。それはまさにどんなに極小な数値を最小単位であると主張したとしても同じである。数値にそこで切断できるような最小単位というものが存在しないからである。
それに反し、例えばパソコンで扱う文字や画像は、それがどんなに滑らかで美しかったとしても、単なる「点」つまり、デジタルの集合体でしかない。例えば肉眼で確かめられるデジタルの例に、新聞の写真がある。どんなに迫力のあるカラー写真であっても、目を凝らすとそれが小さな点の集合であることが分るだろう。
それは普通に見ているフィルム写真であっても同様である。フイルムに撮影された画像は、銀粒子という微小な粒子が感じた光の程度の違いとして数万、数十万集まったものだからである。絵画も鉛筆や筆字による文字も同様である。それは単に絵の具や炭素や墨汁などの色素分子の集合に過ぎない。
分子や原子レベルまで考えたとき、私には今のところ数列と時間以外に連続している事例を考え付かない。もしかしたら量子力学まで行き着くなら、物質や次元といったものにも連続性が関わってくるのかも知れない。ただ、そうなるとそうした世界は私の現在の能力の範囲を完全に超えてしまうので、とりあえずはそこまで考えないことにする。
それでもなお、例えば「命」とか「意思」はたまた「想像」や「怒り」や「愛」などといった物理的特性から離れたものには、連続性というものをを考えてもいいのではないかとの疑問がないわけではない。
ところで、「命」、とりわけ人の命と人以外の生物の命の間には、観念的ではあるが不連続を感じてしまう。それは人間だけが特別に有能で高等だからという意味ではなく、人の命と動植物の命との間には、どこか異質なものを感じてしまうからである。
ただそこまで考えてしまうと、果たして人間同士の命は不連続なのか、「個としての命」そのものは不連続だと考えていいのかなど、疑問は膨らむばかりである。
そうした疑問は、私たちはあらゆる現象がデジタルであり、同時にデジタルで処理や再現ができるかのように考えていることに原因があるのかも知れない。そしてそれはそうした思いそのものがどこまで正しいのだろうかとの疑問につながることでもある。
人が他者(もしくは他の種)の命をコントロールするのは間違いではないか、と先週ここに書いたばかりである(別稿「
死への遺伝子操作」参照)。だが考えてみると、人が他の生物から派生してきたことは事実だが、それを「進化」と名づけること自体、一種の驕りなのかも知れない。人は単に人という生物になっただけに過ぎないのかも知れないからである。
人は確かにコンクリートジャングルを作り上げ、インターネットを駆使するまでになってきた。だがそれを進化だとか成長などと呼ぶのは間違っているような気もする。単に変化の一形態に過ぎないだけのことかも知れないからである。蜂が六角形のハニカム構造の巣を作ることや、宿り木が宿主たる他の樹木に寄生して生きる手段を得たことなどの変化と、特に変わるところなどないようにも思えるからである。
人(私たちが「人」であると許容できる範囲内での人)がいずれ人でないものに変異していく可能性はあるだろう。だがしかし、私たちは地球の歴史の中で生物が発生と変異を繰り返し、そしてやがて絶滅へとその歩みを進めていった歴史を知っている。カンブリア大爆発と呼ばれるまでに新しい種が生まれ、そして僅かを残して絶滅してしまった歴史を知っている。
そうした絶滅は、地球の環境の変化によるところが多かっただろうけれど、中には他種との食物を巡る対立や種そのものが抱える内的矛盾などによる場合もあっただろう。そう考えると、人もまた変化した多様な種のなかの一つに過ぎず、しかもその発生はまだ数十万年前にしか過ぎないのである。それを文明と呼ぶとして、人が文明を得たのは地球の歴史どころか、生物の歴史から見ても、更にはホモサピエンスの歴史から見ても、僅か数千年前のことに過ぎない。偶然に発生し変化した単なる生物の一形態でしかない。
人はどこから来てどこへ行くのか、などと考えるまでもない。人は単なる生物として生まれた一つの形であるに過ぎないことは分っている。地上に繁栄した最強の種などと驕り昂ぶってはいるけれど、そんな感覚を抱いた期間は長くてもここ数千年くらいのことでしかない。
縄張りを争い、食料をめぐる戦いがあり、そして環境の変化が一つの種を破滅へとつなげていく人類の歴史、それは他の多くの種が数億年の歴史の中で辿ってきた絶滅への道すじとそれほどの違いはない。
私が「種」と呼ぶのは、異なる形態ごとの「命」の集団のことである。ある種と他の種とはどこが異なるのか、どこまで異なると種が異なると言えるのかは、必ずしも分かっているわけではない。燕尾服の語源ともなったツバメの尾の先は二つに分かれているそうである。最近、その尾の左右の長さが異なってきていると聞いたことがある。何らかの遺伝の変異によるものなのか、それとも生活する上での必要からきているものなのか、それは分からない。だからこうしたの違いが種の違いと関わりがあるのかどうかも分らない。赤い瞳の猿と黒い瞳の猿とは種が違うのか、色違いや花びら数の違うチューリップは果たしてどうなのかなどなど、種もまた多様である。
種の多様性は、そのまま命の多様性でもある。そしてそうした多様性はそのまま、種と種の境界を不確かなものにする。そしてその不確かさは、そのまま種と種の連続・不連続の問題へとつながってくる。
「ここからは人間」、恐らく私たちはある種の基準を作って、生物を「人」と「人以外」を区分することができるだろう。そしてそれはそのまま、人には人権があり、他方には人権などないとする思いへとつながっていく。でもそれはあくまで「作られた基準」による区別でしかない。その基準は言ってみれば一種の「割り切り」であり多数決による「グローバルスタンダード」でしかない。そうした基準がどこまで正しいのかはつまるところ誰も知らないのである。
果たして人は他の生物と不連続なのだろうか。人を「ホモサピエンス」に区分したのは、単に種の違いを示す指標としてではなく、どこかで私たちが高等生物であることを位置づけたいとする一種の驕りがあったからなのではないだろうか。
太陽の終焉に伴う地球の最後を待つまでもなく、種としての人はいずれ絶滅することだろう。そんなことは明らかである。ただそれは自然淘汰による絶滅ではなく、私にはどこがで人類が自ら発動した自滅のプログラムによるもののように思えてならない。
そしてそうした発動や結果の招来を私は、「それはそれでいいではないか」と思っている。なぜなら、人もまた地球に発生した種の一つに過ぎないと思っているからである。
戦争や内乱やテロを含む暴力の連鎖や環境を無視した身勝手な享楽などなど、人はあたかも巨大化して身動きの取れなくなった恐竜のように、自らが考え出した技術や作り出した享楽をコントロールできなくなっている。適者生存の理屈は、そのまま不適者は生存できないことを意味している。私たちはそうした道を既に選んでしまっているのである。
そしてそうした選択を誤りだとか間違いだなどと言うつもりはない。生物がこれまで数億年をかけて歩んできた道そのものだからである。種が否応なく絶滅へと向かうのは、生物として定められた必須の行方なのだと、私はどこかで頑なに信じているのである。
2016.3.25 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ