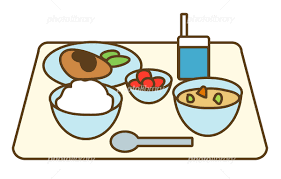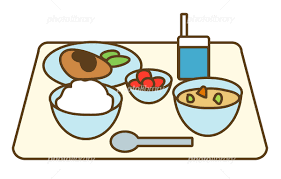これに似た話は、昨年4月にここへ書いたばかりである(別稿「
困ってる人よ、取りに来い」、参照)。だから似たような話題になるのは目に見えている。それでもどうにも私の曲がったへそが、なかなか納得してくれないのである。
コロナが世界に蔓延し、感染者は既に一億人を超えたと言う(WHO、1月29日発表)。そんな中で、日本での生活支援の話である。雇い止め、派遣切り、倒産などなど、仕事を失い更なる低賃金を強いられる人が増えている。
家賃が払えない、電気・水道代が払えない、そして食費の切り詰めへと追いやられる。市民のボランティアによる、食糧支援が始まった。食材の無料支援を超えて、弁当やパンなどすぐ食べられるものの支援、そしてカレーライスや定食など暖かい食事そのものの支援へと、活動は少しずつ手厚くなっていく。
すぐに人気となり、「助かる」、「うれしい」などの声がしきりである。そのことはいい。助かるとか嬉しいと喜ぶ人に、どうのこうのと言いたいわけではない。また、そうした支援そのものにも異論はない。
だが、本当に困っているのは、そうした配給所なりサービス食堂に行くことができない人なのではないかとの思いが、私の脳裏から離れない。そこのところに私の曲がったへそが、どうしても反応してしまうのである。
例えば私が二人の子どもを抱えて飢えているとする。家賃が払えなくて、遠まわしに家主からは立ち退きらしき言葉が発せられている。先月までの日雇いの仕事は、今のところ後はないと言われている。貯金も間もなく底を着く。水道も電気も節約して、最小限度にしている。
あとは食費をつめるしかない。生活保護がチラチラ頭を掠めるけれど、「やつぱり自力で頑張ろう」とどこかでやせ我慢している自分がいる。
電気代の節約でテレビも思うようにつけていないけれど、最近食事の無料提供してくれるところが東京や大阪などにあると聞いたことがある。だが札幌にもあるのかどうか、そんなことを知らせてくれる人はいない。とりあえず電話は生きているが、ここ数ヶ月、うんともすんとも音が出たことはない。
「助けて」と言いたい気持ちと、「自分で何とかするのが人間だ」と思う気持ちとが、心の中でせめぎあっている。そうした迷いを相談したいけれど、相談先の所在も電話番号も知らない。
仮に分ったとしたところで、我が家の隣にあるというならまだしも、住所からその場所へ行けるとは限らない。薄汚れたコートの身に、雪道を歩いてそこへ辿り着くことなどまず無理である。
携帯電話があって、SNSなどから各種の援助情報が伝わってくる環境にある身ならいいが、私にはない。携帯を持っているような人だったら、恐らく自力で動けるだろう。場合によっては、マイカーを持っているかもしれない。
私に類似した仲間たちの多くは情報弱者なのである。そしてほとんど移動手段を持っていないのである。それは老人に限るものではない。情報弱者には、情報が伝わらないのみならず、行きたい場所に移動する手段さえも乏しいのである。
携帯を持ちマイカーを持っているからと言って、その人たちを弱者でないとは言わない。でもそうした人たち以上の弱者が、世の中にはまだまだ沢山いると思うのである。そしてひっそりと目立たないように隠れているのである。
ひもじいと飢えているとは違うのかも知れない。でも、食糧支援を「うれしい」と感じる人よりも、もっともっと小さい「うれしい」を求めている人がいる。それか情報弱者なのである。食料配給所のあることも、そんなシステムが存在していることも知らない人たちが、途方に暮れているのである。
そこへ食料を届けると言うのは、実はとっても余計なお世話なのかもしれない。救いを求めないのだから、放っておいても少しも構わないのかもしれない。でも私はそんな放っておくことそのものに、どこか後ろめたさを感じてしまうのである。
なぜならそうしないと、その人たちに食料は届かないからである。飢え死にするようなことはないとしても、ひもじさは休まることなく続くからである。
だから私にはこうした「来た人にのみ提供する」と言う食堂システムが、「改良の余地がある」では済まされない、どこか致命的な欠陥が内蔵されているような気がしてならない。そしてそのことが私を、耐えられないような気持ちにさせるのである。
2021.2.14 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ