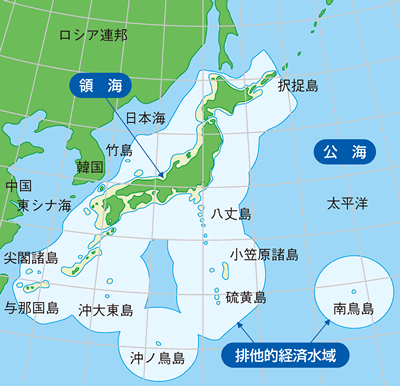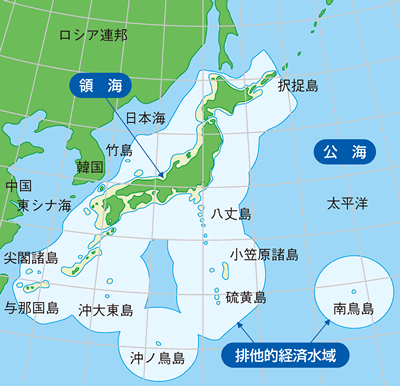周囲100メートル以上を島と言うらしいし6000余の島の中で人の住んでいるのは400程度らしいから、島とは名ばかりで海面に僅かに頭を出しているような岩場みたいなものも含まれていることだろう。私はその実態をまるで知らないのだが、単に日本が周囲を海に囲まれた小国であることだけではその数の多さを説明し切れていないような気がする。単に四方が海であるだけでなく、海そのものへの支配が広大であることにこそその要因があるのではないかと思えたのである。
65年前に日本は戦争に負けて、ポツダム宣言やカイロ宣言などでその領土が現在の形になったと言われている。もっとも小は戦国時代の国盗り物語などから、十字軍の遠征、現在の世界の民族紛争や独立運動などを見るにつけ、領土と言うのが争いの結果による単なる線引きでしかないことは歴史が示すところかも知れない。
国際的な領土や領海の概念、または誰もが認める領土や領海の範囲がどのようにして決定されるのかを私はきちんと理解しているわけではない。一口に日本の国といったところで、一つの「区画された土地」を国土と呼び、その周囲に海があるときは12海里(約22Km)までを領海、更に領海を含むその外側12海里までを接続水域、そして海岸線から200海里(約370km)までを排他的経済水域と呼んで、それぞれに若干の効力の違いはあるもののその国の主権が及ぶとされている。この外側は公海である。
ところでそれが旧日本軍の単なる一方的な宣言に過ぎないのかも知れないけれど、第二次世界大戦における日本の領土は、それを単に支配とか占領と呼ぶことの妥当性はともかくとして日本沿岸から東南アジアを経て遠く南半球のニュージーランドの半分までを含む地域にまで達したことを何かの機会に見たことがある。その地図に見る日本の国土はあまりにも小さく、それと比較して支配したとされる海域は異常なほどにも広大な面積を持っていた。
それがポツダム宣言で現在の姿になったことを否定したり異議を唱えるべきだと言いたいのではない。ポツダム宣言そのものだってソ連の締結国への参加のずれなどが現在の北方領土問題の混迷のもとになっているとも言えるのだから、そのために様々な困難な外交が求められていることだって了解しているつもりである。
だが私はこうした領土に関する知識不足を自らに認めたうえでも、どこか日本の領土としての6000余の島の数はどこか多すぎるような気がしてならないのである。それは日本の領海が、北海道・本州・四国・九州などを世界地図で確認できる形としての日本の姿から見て、やっぱりどこか広すぎることに起因しているのではないかと思えるからである。
単に国土と海域との比較だけを捉えて領土の概念をどうこう言いたいわけではない。例えば100平方メートル一個の島から形成される独立国があったとして、そこを基点として領海、接続水域、排他的経済水域などをコンパスで囲んでいくなら、国土との領海等の面積比較論に意味がないだろうことくらい明らかだからである。
それはそうなんだけれど、日本の国土面積(つまり土地としての面積)が38平方キロメートルであるにもかかわらず、上記領海や経済水域を含めた海域の面積は447万平方キロメートル(国土の11.8倍)にも及ぶと言われている今の姿はどこか気になる。もっと簡単に言うと、日本の国土面積は世界で60番目であるのに対し海域面積は世界第6位まで膨らむのである。私はこのアンバランスが6000もの島の背景になっているのではないかと思っているのである。
海を持たない国なんてのは世界にたくさんあるだろう。だからと言ってそんな国と日本を比較することに意味はない。ただそれでも事実上管理できないまでに広大な領域を持っているというのは、国としてどんな意味を有しているのだろうかと思ってしまうのである。もちろん私は日本の海上自衛隊と海上保安庁の役割分担の違いや持っている力などをきちんと知っているわけではない。だからこんなことを言っても説得力はないのかも知れないけれど、どうしても現在の日本がその領有する海域をきちんと管理できるだけの設備なり機能を持っているとは思えないのである。
私はその能力を軍事力に求めるつもりはない。だが実効支配を維持していくためには、外交的な能力も当然必要ではあるけれど、事実上の管理能力を背景とした外交もまた必須ではないかと思うのである。
そしてその管理の背景には
「領有権に争いがある場合には『実効支配』の実績が重要。有効な管轄を実現する」と公式に述べたとされる中国海洋当局の見解(朝日新聞、2010.9.30、私の視点、元外務省条約局長東郷和彦氏の投稿から引用)のような意見にまともに対抗し得るだけの覚悟が必要なのではないだろうか。そしてその覚悟とは
「外交が失敗したら戦争になる環境におかれていた戦前の外交官が、身命をかけて努力した課題に他ならない」(同上、東郷和彦の投稿)とするまでの覚悟を秘めたものになるのではないだろうか。
私に外交についての知識は皆無と言ってもいいほどである。だからこんなところで拳を振り上げたところで蟷螂の斧さながら説得力に欠けるとは思うけれど、今回の尖閣列島魚釣島の近くで監視している海上保安庁の船舶に故意にぶつけたとして公務執行妨害で逮捕された中国漁船船長の逮捕から釈放までの経緯(別稿「
堕ちていく司法」参照)や北方領土をめぐるロシアとの交渉などを見るにつけ、そこまでの日本側の覚悟がどうしても見えてこないのである。そしてそれは「きちんと管理できないでいる日本の領土」と言うのは、果たしてどんな意味を持っているのだろうかとの疑念にもつながっていくのてある。
宗教対立、部族対立、不満分子の政権打倒、軍部による革命、他国からの干渉などなど、こうした武力による争いと「戦争」との区別を私は知らない。状況的には第三次世界大戦などと呼ぶほどの事態は起きないように思えるから、こうした日本周辺の領土問題も結局は外交の形で対処していくしかないのかも知れない。日本に祖国は存在しているのか、日本人に祖国意識は残っているのか、祖国のテーマは私の中でいつまでも未解決のまま渦まいているだけだけれど、それでも日本の主権を諸外国に示すための力が常に政治には求められているのではないだろうか。
時に外交は国民から隠蔽されることがある。「外交ってのはそんなものなのだ」と言われてしまえば反論するだけの実力はないし、例えば外交文書などが国民に知らされるのが40年も50年も経てからになる現実も知らないではない。ただそうしたことはまた同時に国民がツンボ桟敷に置かれていることでもある。果たして国民に知らせないこと、結果だけを神託のように与えることが外交なのだと、私たちは頭から思い込んでいていいのだろうか。
もちろん日本を守るために死に物狂いで交渉に挑んでいる日本外交がどこか極秘裏に存在しているのかも知れない。しかし、そうした事実を国民が何にも知らないのだとしたら、仮に「何の努力もしていない外交」や「漫然と放置したり間違った方向に進もうとしている外交」などがあったとしても、国民はまさに「なんにも知らないまま」過ごしてしまうことになる。
外交と秘密主義は諸外国の動きなどを想像する限り密接不離なのかも知れないけれど、もしかしたらそうした秘密主義を頭から信じてしまうのは私たちが誤った信仰にコントロールされているからなのかも知れないとふと思うことがある。情報が一箇所に集中してしまい、その中で国民の意思までもが統制されてしまうことの弊を、私たちはこれまで何度も身にしみて味わってきたのではなかったのか。それでもまだ私たちは、「誰かがなんとかしてくれる」とののん気さをいつまでも持ち続けていていいのだろうか。
2010.10.13 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ