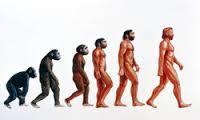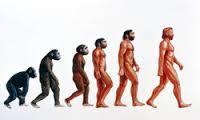人は神が自らに似せて作ったと聖書は説き(旧約聖書 創世記 第1章 26節、27節)、ダーウィンは進化という過程を経て原始生物から人類が誕生したと説いた。進化論が優勢を極めているけれど、人類もまた分岐を繰り返し絶滅を繰り返した生物の末裔として、「たまたま生き残った種」に過ぎない。
種の分岐という形で進化しそして行き止まりになった種、つまり絶滅を辿った生物は思った以上に多い。ほとんどの生物の種は90数%が絶滅しているとの説もある(理不尽な進化 遺伝子と運のあいだ、吉川浩満、朝日出版社)。人類の祖先もまた、絶滅を繰り返した多くの進化・変化の中から生き延びてきた。
私が記憶している人類進化の過程でも、ジャワ原人は70万年ほど前に、北京原人は50万年ほど前に、ネアンデルタール人も10万年ほど前に絶滅している。つまり長い淘汰を超えてネアンデルタール人と呼ばれる人種まで進化してきた人類も、何が原因なのかは分らないけれど進化の行き止まりを迎えたのである。そして現在の人類にまでたどりつくことはなかったということである。
私たちそうした数多に分岐した人類の中から、絶滅を免れたクロマニヨン人につながる系列として生き残った種からたどり着いたと言われている。クロマニヨン人は新人類と呼ばれているが、約三万年ほど前に他の人類から分岐したと考えられている。人類の歴史は人類亜科と呼ばれる種の発生とされている約500万〜600万年前から始まる。その後、猿人、原人、旧人類を経て新人類へたどり着く。
だから一口に人類の歴史と言っても、どこから人類と呼べばいいかは、その語ろうとする物語の意図なり目的によって異なると考えてもいいだろう。
私が今考えているのは、化石としての人類とか二足歩行をはじめた霊長類などのことと言った類のことではなく、人らしく生きはじめた歴史にあるので、人類の発祥を私たち人類の共通の祖先であるクロマニヨン人へと分化した時点を基準にしていこうと思う。
ただ、スペイン北部のテルタミラ洞窟の壁画は約36千年前のクロマニヨン人が描いたとされていることからすると(2016.9.18、朝日新聞)、人類の歴史の分母は約4万年くらいと考えてもいいだろう。地球は誕生してから46億歳と言われているので、それと比するなら4万年なぞ一瞬の間ではあるが、人の一生を100歳と考えるならそれなりの長さを持っている。とは言っても仮に20歳で子どもを生んで人類の世代が続いていくと考えたとしても、たかだか2000世代くらいにしかならない短さである。
ところで人類と呼ぶときに、その基準には色々あるだろうけれど、今でも続く習性に思いを馳せるなら「衣・食・住」に集約されるのではないだろうか。文化、芸術、哲学などなど様々な分野へと人は自らを進化させてきたけれど、基本にあるのは集団による社会生活であり、第一に食べること、次いで住むこと、そして着ることだったのではないだろうか。
人類の文化がいつころから始まったかと問われるなら、その答えはとても難しいだろう。食べることそのものだって文化であり、暖の取れる住居もまた文化である。また身に衣類をまとうことだって、たとえその目的が防寒にしろファッションにしろ呪術にしろ、それもまた文化であることを否定はできないだろう。
それでも中国三千年の歴史と言われたり、ピラミッドの歴史などを聞くにつけ、人が人らしく生きはじめたのはたかだか数千年前であろうことは容易に想像できる。それまで人は穴の中に住み、野生動物の狩りと果樹などからの採集でひたすら世代をつなぐこと、生き延びることだけを考えてきたのである。
時間の経過をキリストの誕生を基準とした西暦で刻むことが、どこまで妥当するかは分らない。それでも私たちは縄文時代まで穴の中で生活していたと言われている。それに次ぐ弥生時代が紀元前300〜後300年と言われているから、人が人らしく生きはじめたのはその頃からであると考えてもいいのではないだろうか。住居は穴から地上へと解放され、食は栽培や飼育などからも得られるようになってきたからである。
だとするなら人類の文化と呼べるような歴史は、たかだか二〜三千年にしか過ぎない。それにもかかわらず、私たちのいま経験している時代の変化はまさに異常である。
数学に指数関数というのがある。グラフで表すと、最初はゆっくりと上昇していっている変化が、時の経過と共に突如として垂直とも思われるほどにも高位の値へと変化していく。
私の人生、私の生きてきた時代そのものが、指数関数の垂直時代とも言えるような変化の只中にあったのではないかと思っている。もちろんそうした変化の度合いを、ゆっくりと感じるか凄まじい早さだと感じるかは、人により様々だとは思う。石ころを武器にしていた人類にとって、ある日突然に青銅や鉄に取って代わられることはまさに凄まじいものだったかもしれない。それでもそうした変化は数代とか数十世代といった長い時間の中での変化だったと思う。それが今や、私の生きてきた時代そのものが博物館に展示されるようになってきた。
人工衛星が始めて地球の回りを回ったのは、私が高校三年生のときだった。就職試験の面接で、「お前たちは揃って人工衛星の話しかしない」と言われたことを記憶している。夕張という北海道の片田舎の炭鉱町での暮らしではあったけれど、家庭にはかろうじてラジオはあったものの、テレビも電話もない。公道もぬかるみと轍(わだち)が続き、走っているのは主に馬車で、自動車や三輪自動車が珍しい時代だった。
それが今はどうだろう。携帯電話やパソコンが当たり前になり、人工知能は時にチェスや碁の名人と呼ばれる人の能力をもしのぐようになった。宇宙は数万とも数十万とも言われる「デブリ」(壊れた人工衛星の残骸や部品などのゴミ)で覆われ、タクシー代わりに飛行機が人を運ぶ世の中になった。妊娠は人工授精や母体交換などでコントロールされ、遺伝子操作によって子どもの選別や作物の改良、新たな医薬品の開発などが氾濫する時代になった。
そして更に加速しているのが暴力や貧困や差別である。兵士のみによっていたはずの戦いは、いつの間にか一般市民を超えて小児や幼児を巻き込む無差別殺戮にまで拡大し、憎悪や対立は世界のいたるところに蔓延している。地球温暖化一つをとっても、私たちは引き返すことなどできないと言われるところまで来ている。
世界の多くの建物は、当時考えられていたバベルの塔の高さをあっさりと超えてしまったことだろう。そしてギリシャ神話のカサンドラの予言が無視されたように、人は他者に耳を傾けることを拒否し続けている。私はかつてこの場で人類の自滅のプログラムは既に発動されてしまっているのではないか、人間不信の思いはこれからも解けることはないのではないかと書いたことがある(別稿「
バベルの塔の教訓」、「
カッサンドラの呪い」参照)。
ドイツ人ヴァルター・ベンヤミン(1892〜1940)は、19世紀を「集団的意識の方はますます深い眠りに落ちてゆくような時代(ないしは時代が見る夢である)」と書いた(鹿島茂 『パサージュ論』熟読玩味 青土社 1996年 P13、116)。そうした集団が見ている夢は、今の時代もそのまま続いているように私は感ずる。
「人はどこから来たのか、どこへ行くのか」の言葉は、もう使い古されて何の感慨のないまでに劣化しているかも知れないけれど、それでもなおその問いと答えへの希求は、依然として私たちに求め続けられているのではないのだろうか。
2016.9.16 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ