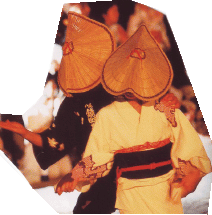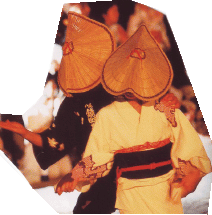”水音が聞こえない”
そう思って、太田とめは足をとめた。
高山線の八尾駅近くにある自分の家から、一気に長い坂ひとつをのぼって来た。七十歳をこした身にはこの坂がこたえる。越中八尾と呼ばれる富山県婦負(ねい)郡八尾町には、坂の町という別名があって、ゆるいくの字なりの急な坂が、奥へ奥へとのびている。
高橋治「風の盆恋歌」はこんなふうに始まる。作者は直木賞作家だと聞いたが、なんとか賞にこだわって小説を読む習慣などなかったので、この本を知ったのは恐らく誰かから勧められたのがきっかけだったのだろうと思う。
それぞれに長く結婚生活を続けてきた男と女の不倫の物語だと言ってしまえばそれまでだけれど、若い頃に遂げられなかった愛の軌跡は、おわらの踊りを背景に不倫のイメージを超えて読む人の心に静かにそしてあたかも墨絵のように訴えるものがある。
だからどうしても風の盆を見たかった。八尾は富山県である、さすがに札幌からは遠い。そんな時苫小牧〜名古屋フェリーの往復チケットが知人から格安、しかも個室で手に入るチャンスに恵まれた。もちろん名古屋と富山とは太平洋と日本海のまるで正反対の位置にある。
だがかつて東京での研修中に飛騨高山へ旅行したことがあり、岐阜方面から高山線で高山一泊、翌日名古屋方面へ戻ってその日のうちに東京へ帰る予定が、高山駅で上り下り両方向に列車が停まっていたせいもあって反対車線に乗ってしまい、気がついた時は富山が目前であわてた記憶がある。そのときは折りよく富山から夜行の上野行きがあって、どうやら翌朝の授業に遅刻せずに間に合うことができたという際どさだった。
ただこのことは考えて見れば名古屋と富山とは正反対ではあるけれど、高山線の始発と終点みたいなものだから丸っきりの見当違いというほどの違いではない。名古屋へ車で着いたのなら八尾は行動範囲に入れてもいいのではないかと勝手に思い込む。
早速計画にとりかかろう。風の盆は台風の襲来で慣用語となっている210日に合わせたこの地方独特の9月1日から三日間の少し遅れた盆踊りである。フェリーは8月29日の予約がとれ、名古屋港到着は31日早朝である。少し早い到着だからこの間の日数を利用して念願の「野麦峠」(別稿「
野麦峠に立つ」参照)、「宇奈月温泉」(別稿「
宇奈月温泉と最高裁判所」参照)にも寄りたいし、なんなら「安宅関」(別稿「
安宅関」参照)にも行きたいと、思いは膨らむばかりである。
さて風の盆、問題は八尾での車の置き場である。人気の高い風の盆は人、人、人でごった返すと聞いているし、街の中は全面的に駐車禁止である。そのことは事前に町役場や観光協会のホームページで確認済みである。しかも民宿も含めて旅館が一件もないことも分かった。しかも風の盆は夜を徹して胡弓が奏でられ踊りが続くと言われているではないか。
それにまともに付き合うためには八尾に親戚を作るか、野宿するしか方法がないのである。車で野宿する覚悟はとうにできているが、町が用意しているという駐車場は遠く4キロ以上も離れた場所にあり、いかに健脚でも風の盆の見物や休憩で気軽に往復できるような距離ではない。しかも終バス時刻の決められた送迎バス利用ではなんとも物足りない。ハイヤーもこの祭りの混雑では利用は諦めた方がいいという。
街中での駐車禁止に素直に諦めきれなかったことと街の様子を探るためもあって、街中を何度も何度も車で走り回る。そもそも狭い通りの続く坂の町であり、河原も含めてやはり駐車できるような場所など見つかるはずもない。段々と夕暮れが迫ってくる。いよいよ公共駐車場を使うしかないかと思った頃、天満町の公民館から少し下った所に小さな空き地を見つけた。街の中を流れている井田川近くの坂の下で十三石橋から続く屋台行列の始まり地点まで1分足らずの場所にどうやら車一台やっとの空き地が見つかった。
JR八尾駅と踊りの一番賑やかな諏訪町とのちょうど中間くらいのおあつらえ向きの場所である。車から離れて橋の上からしばらくの間、お巡りさんや祭りの関係者や場合によっては地主などがクレームをつけにこないかとそれとなく様子をうかがっていたがどうやら大丈夫のようである。
近くの商店街で仕入れてきたすきやきもどきの肉鍋を車の傍で作り夕食とする。缶ビール一本飲んでさて街へと散策に出かけようか。これからが風の盆の本番である。この時のためにここへ来たのである。
街のいたるところに「踊り場」と称する舞台があり、そこで踊るのが明るいうちの通例らしい。諏訪町は坂道の行灯がきれいに揃っていて観光客で賑わっている。西町、鏡町、下新町、今町、東町、天満町・・・、町々がそれぞれに自慢のグループを作っていてそれぞれに踊りを披露している。
若い娘はいずれもそろいの衣装に黒い帯と顔を隠す深い笠の装いである。細い襟足が笠からのぞいていて、そこにかかる巻き上げた髪のほつれがなんとも美しい。
夜が進んできた。諏訪町の一本下の通りの上新町では見物客を巻き込んだ長大な盆踊りが始まった。片道500メートルはあるだろうか、道路一本を丸ごと使った細長い輪踊りである。北海盆踊りにも参加したことのないこの身にとってみれば、異邦の地とは言え輪の中に混じるのには多少気後れがないではない。旅の恥は掻き捨てとも言うけれど、別に恥ではないだろうがなんとしても照れが先に立つ。
だが今夜は異邦の地の異邦人である。踊るためにこの地に来たわけではないけれど、思い切って輪へと飛び込む。なんともさまにならない手の動き、足の運びである。大きな長細い輪の中には何箇所か小さな踊りの台が設けられていて地元の男女がその上で手本を見せてくれている。見よう見まねでそれについていくしかないが、隣で踊っている観光客のおばちゃんの真似でもとりあえずなんとかなりそうである。
夜が更けていく。午前0時、輪踊りはまだまだ混雑とも言っていいほどの観光客の人ごみと熱気を残したまま突然に終わりを告げる。だが風の盆はこれで終わるのではない。これからが町の人々の自分たちのために踊るいわゆる「町流し」の時間である。輪踊りが終わって汗ばんだ肌に9月の風は少し冷えてきた。寝袋持参の観光客も多いと聞いたが、私には狭いながらもきちんとした鉄の小部屋がすぐ近くにある。気の向くまで風の盆に付き合うことにしよう。
町流しは少人数の歌と三味線と胡弓と踊りである。男踊りの勇壮さもさることながら、やっぱり女踊りのゆったりとしたなまめかしさ、時に可憐な指の動きなどに踊り手自身が楽しんでいる姿は見る側にもその気持ちが伝わってくる。
八尾の町には風の盆に関係なく稽古のおわらの音が流れる。それを聞くたびに、とめには今にも玄関が開いて都築とえり子が入って来るように思えてならない。
こんな一節で小説「風の盆恋歌」終わる。だが今日はまだ初日である。瀬戸内寂聴がエッセイ「寂庵こよみ」(北海道新聞平12.9.24)の中で京都祇園の女将にこんな一言を言わせている。
「へえ、先生も(風の盆に)おいでやしたの?。あれは最後の日の夜明け方が一番よろしおすえ。・・・あの哀愁が何とも云えませんなあ。」
ここまで言われてしまったら、どうしたって最後の日まで付き合わねばなるまい。風の盆三日目を抜かしたのではこれまで抱いてきたこの旅への長い想いが泣くと言うものではないか。帰りのフェリーまでにはまだたっぷりと余裕がある。
さりながら、明日の9月2日はこれも有名な岐阜の郡上八幡で時期遅れながら郡上踊りが開かれるとの情報も得ている。風の盆の二日目を抜いてしまうのはなんとなく後ろ髪を引かれる思いだが、郡上踊りの魅力にも抗しがたい。ならば明日は郡上八幡へ行き、再び三日目にこの地へ戻ってくることにしようと決める。
まだ夜明けの白みには遠いけれど午前3時を過ぎた。町も静かになってきた、車へ戻って一眠りすることにしよう。野宿は今日で二日になる。明日は民宿へでも泊まって少し体を労わるのもいいだろう。ネットで何件が候補の民宿も見つけてある。
・・・風の盆三日目の様子は後編でどうぞ(前編おわり)。
後編はここをクリック
2007.4.17 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ