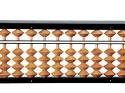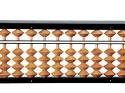世の中コンピューターがいたるところに組み込まれるようになって、コンピューターなしではロケットもインターネットも身近なテレビやCDすら利用できない時代になってきている。ところで少なくとも私が出合った頃の「コンピューター」の日本語訳は「電子計算機」であった。つまり、電気を使って計算するマシンの意味である。
やがて稚拙ながら自分でコンピューターの勉強を始めたり、マイコン、パソコンと呼ばれる得体の知れないマシンを手に入れてプログラムを打ち込んだりするようになると、コンピューターのいわゆる「天才的な判断」と呼ばれる能力も、つまりところは高速の計算によるところが大きいことが理解できるようになってきて計算機と名づけられたわけも了解できるようになってくる。
ともあれ人は様々な道具を使って計算してきた。数の発見は恐らく数えることの必要から生まれたものだろう。人数にしろ、穀物の収穫にしろ、暦や税にしろ、人の生活の中で数えることの必要は避けられない現象であったことだろうからである。
ここで数えることの歴史を遡ろうと思ったわけではない。ただこうして70年も生きていると、けっこう私の身の回りにも計算に係わる様々の道具との付き合いがあったことが思い出される。
① 指
まあ誰でもそうだろうけれど、数えることの最初は恐らく自分の指だろう。人間の指が10本なので10進法が定着したらしいけれど、そこまで考えなくたって「ひとつ、ふたつ・・・」と指を折って数える手法は物心ついた頃からの習慣であった。もちろんそれは親から教えられた手法だったかも知れないけれど、「数える」と言う人間に備わった必然でもあっただろう。
指を使った数え方の中で珍しい経験をしたことがある。例えば片手の五本指でいくつ数えられるかと言う質問を誰かから受けたことがあった。まあ、単純に考えて「いくつまででだって数えられるだろう・・・」が最初の直感であった。左手で(右利きなのになぜか数える時は左手が多いのはどうしてなのだろう)親指を曲げ、人差し指を曲げ、一つ、二つと数えていく。五つになったら全部曲げた指から逆に小指を立てて「六つ」としていくのである。全部広げて「十」だから、また親指を曲げて十一とやればいい。そうすればいくつまでだって数えることができると思ったのである。
だが困ったことが起きることに気づいた。例えば小指以外の指全部を曲げた状態は果たしていくつなのかを必ずしも特定できないことである。数を声に出して言っているときは良いけれど、握りこぶしから小指だけを延ばしたこの形が、果たして「四つ」なのか「六つ」なのかは誰にも分からないのである。それは自分に対しても同様であることを意味している。「十四」も「十六」も「二十四」も「二十六」もそれぞれ同じ指の形をしていることに気づくからである。これでは「いくつでも数えられる」ことにはならない。だとするなら、指が5本なのだから「一から五」まで(正確には指を全部開いたいわゆるジャンケンのパーの状態、つまりゼロを含めた六個)しか数えられないことになる。
これでゼロから五までは確実に数えられることになるが、ただこの数え方の欠点は「一度曲げた指はその状態を維持しなければならない」ことにある。「一」と数えて曲げた親指は二度とその状態を変えられないのである。そこでこのルールを変更することにする。つまり、「一」と数えて親指を曲げたとする。次に「ニ」と数える時に人差指を曲げると同時に親指を伸ばすのである。この状態は片手の指五本のうち、人差し指だけが曲げられている。こうした指の形はこれまで私が理解していた数え方の中には表われてこない。そして「三」は人差し指を曲げたまま親指を曲げる。そして「四」は中指を曲げてそれまで曲げていた親指と人差し指を伸ばすのである。こうした作業を繰り返しながら数えていくと、五本の指で「31」(全部の指を伸ばした状態を「ゼロ」という一つの状態を示していると認識するなら「32」)まで数えられることになるのである。因みに両手の指10本盆部を使うと、1024まで数えることができるのである。
こうした手法を自力で発見したのではないから、恐らく誰かに教わったのだろう。それも高校生を超えていたような気がしている。そしてこうした数え方が二進法、つまり指を曲げるか延ばすかという二つの状態を「1」と「0」に対応させる情報の表現方法だと知った初めてのできごとだった。私の中に新たに二進法という知識が取り込まれた最初の経験でもあったのである。
② 算盤(そろばん)
そろばんは小学生の頃から学んでいたような気がしている。自分の身長よりも横に長い教材としてのそろばんが黒板の上や教室の隅に置かれていたのを記憶しているから、おそらく寺子屋時代からの日本の教育の伝統でもあったいわゆる「読み・書き・そろばん」は私たちの小学校教育にもそのまま引き継がれていたということでもあろうか。
爪楊枝のような串に一つの小さな玉を差込み「五玉」と呼んで一つで五の単位を示す。その玉が上下に玉一つぶんだけ動いて上にあったらゼロ、下りていたら五を示したのである。その五玉の下に固定された枠があってその下に五玉と同じ大きさの玉が四つ縦に並び玉一つ分の余裕を持たせて差し込まれていた。この玉は全部が下に下りていたらゼロを示し、一つ上がっていたら「一」、二つ上がっていたら「ニ」・・・、同様に「三」「四」であり、先ほどの五玉と併用することによってゼロから「九」までの数を表すことができるのである。そしてこの五個一組の玉の列を横に並べることによって桁を示し、それぞれを「一」、「十」、「百」、「千」、「万」・・・の単位に位置づけることによって、いくらでも(そろばんとしての物理的な重さや持ち運びの便利さなどの制限はあるにしても)置く数値を拡大することができたのである。
任意の場所の縦一列を使ってゼロから九までの数字が置けることは説明した。その左隣の一列を「十の位」として例えば六を置き、右の「一の位」に三を置くことで「63」がいとも簡単に表示できることも言った。一つずつ増やしていって一の位が満杯の九になったら左隣りの十の位に一を加え、一の位の玉を五玉を上に一の玉四つを全部下に下ろす(つまりゼロにする)ことで足りる。これが計算の基本である。
もちろん一つずつ加えていくわけではない。例えばある数に八を加える場合を考えよう。一の位に残っているある数が0か1なら8を加えることは容易である。だがそれ以上になると「8を加えるとは10を加えて2を引くことだ」と理解するのである。例えばある数が2なら、左の十の位に1を足して同時に一の位の2つの玉を下へ下げるのである。この一の位の玉を2つ下げることを理解できるならある数が3、4の場合も同様に計算できる。ところが5になるとそう簡単にはいかない。その場合には2減らすと言うことは五玉を上げてゼロにし3を加えるという動作に変わるのである。つまり十の位に1をたて、一の位の5をなくし(0にし)同時に3を加えるという三つの動作が必要になるのである。
こうした作業は例えば筆算による計算に比べるならどちらかと言えば面倒な作業である。しかし、8と言うのは10の補数として2であること、2は5の補数として3であることなどを理解してしまうと、練習を重ねることによって指が勝手に動いてしまうまでにこの動作には慣れてくるのである。こうした指使いは加算する数が変化しても同様に理解できるし、引き算についても同様である。そうした訓練を重ねていくことによって、そろばんは数字をあるイメージとして捉えることが次第にできるようになってくる。
私のそろばんの実力は、日本商工会議所検定三級という「まあとりあえずは使い物になる」程度のままで停止してしまったけれど、初段、二段などと実力を上げていくに従い、そろばん検定であるにもかかわらずそろばんを使わない(つまりそろばんの盤面を頭の中でイメージするだけで計算ができる)暗算でも答えを出せるまでに進化するようである。そこまでの才能は私には遠い出来事であったし、及びもつかない辺境の実力ではあっただろうけれど、補数の実感や数字が一つのイメージとして捉えることができることをそろぱんは教えてくれたのであった。
考えていた以上に私の計算機への思い込みは強いようです。まだまだ話し足りないようなので稿を改めることにしました。この続きは「私の計算機遍歴(2)」に譲りたいと思います。
私の計算機遍歴(2)「計算尺」へ
リンク 私の計算機遍歴(2)「計算尺」 (3)「手回し計算機」 (4)「電卓」 (5)「関数電卓」
2010.9.2 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ