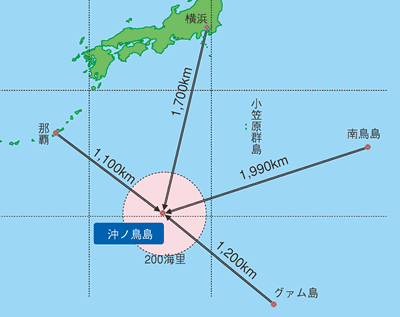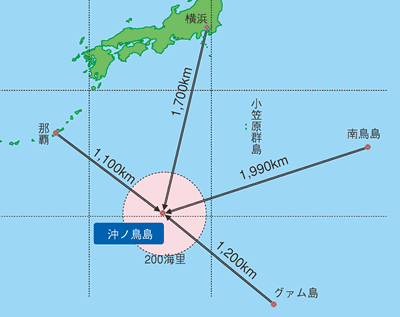① 北方領土
これについては私が北海道に住んでいてこの問題を耳にする機会が多いこと、根室や知床を旅して目の前のあまりにも近い島影に驚いたことなどから何度かここに取り上げたことがある(別稿「
北方領土の日」、「
北方領土」、「
分かり易さの裏に潜むもの」参照)。
ロシアとの主張の違いはそんなに複雑なものではない。ロシア(ソ連)はヤルタ協定やポツダム宣言及び日本の降伏文書によって既に決着されており、両国間に領土問題は存在しないとの主張が基本である。それを補強するかのように対日平和条約及び日ソ共同宣言は、この事実を確認したに過ぎないのであって日ソ共同宣言での歯舞・色丹両島の引渡しはソ連の善意であるにもかかわらず日本はこれを拒否したとしている。
日本の主張は引用した別稿にも書いたけれど、北方領土は日本固有の領土であるを基本とし、対日平和条約で放棄した「千島列島」には北方領土4島は含まれていないこと、ヤルタ協定は連合国間の密約であって日本を拘束するものではないを基本としている。
平和条約締結前に占領地域を自国領土へ編入したソ連の措置は有効か、対日平和条約は当事国でないソ連に及ぶのか、日ソ共同宣言で行った合意をその後の日米安保条約を理由として一方的に変更できるのかなどが問題視されることになる。ただこうした問題点の解決に加えて現実として実効支配がソ連に移っている現状とどう折り合いをつけていくのかは、まさに外交の問題だと言えよう。
② 竹島(韓国名、独島)
日韓は最近特に北朝鮮問題を巡ってアメリカと接近しており、日米も離れがたい関係にあることからそれほど目立った対立は起きていないこともあってここに取上げた記憶がない。それでもそれは外交が互いの対立を避けようとしているためであり、平成17(2005)年3月、島根県が100年前の管轄を告示した日である2月22日を「竹島の日」とする旨の条例を制定するなどで、依然ぶすぶすくすぶり続けていることに変わりはない。
韓国の主張は古くから独島は韓国領土であるが基本であり、そもそも無主地ではなかったのだから1905年に日本が行った領土編入措置は無効であるのみならず韓国政府に通告もされなかったことを基本とするものである。またカイロ宣言ほか戦後の一連の措置(例えば1946年の連合国総司令部覚書では竹島を日本から政治上・行政上分離し、日本の権力行使を停止していることなど)からも韓国領土であることは確認されているとも主張している。
これに対し日本も韓国と同様古くから日本の領土であるとの主張を基本としており、1905(明治28)年に日本は竹島が日本の領土であることを閣議決定し、それを受けた島根県知事が同島を自らの管轄地とする旨の告示を制定したことを根拠としている。なお連合国総司令部覚書は占領下における暫定措置にしか過ぎないし、対日平和条約により日本が放棄した地域に竹島は含まれていないことも引き続き日本の領土であることを示していると主張する。
互いに「もともと我国の領土である」と主張しているのだから折り合いをつけることは難しいだろう。日本による1905年の閣議決定や島根県の告示の国際的な効力、カイロ宣言や対日平和条約に及ぶ一連の戦後処理の位置づけや解釈などを互いにどう理解していくのかが問題となろう。韓国は最近この海域での実効支配を強めてきていると聞く。日韓が友好的である中で、まさに外交が問われているのだと言えよう。
③ 尖閣諸島
これについてもここに取り上げたことがある(別稿「
魚釣島の領有権」、「
堕ちていく司法」参照)。中国側は直接領土として主張するのではなく、尖閣諸島は台湾に属しその台湾が中国の領土であることを根拠とするものである。そして沖縄返還協定における「返還区域」へ尖閣諸島を組み入れたのは日米における不法な行為であるとする。もちろん日本は引用した「魚釣島の領有権」にも書いたとおり、先占(いわゆる早い者勝ち)として1895年に領土として閣議決定という形で取得したものであり、その後も引き続き実効的に支配してるとするものである。
さてここでの問題は沖縄返還協定締結に至るまで尖閣諸島は中国の領土であったのかであり、それまでなんの主張もしてこなかった中国が1971年になってから突然に抗議してきたことの意味である。海底資源であるとか軍用・商用の艦船が東南アジア諸国との間を自由通行できる権利の確保などがからんでいるとも言われているが、これもまた外交の重要な登場場面であろう。
④ 沖ノ鳥島
これは領土問題とはいささか趣きを異にする。この島の領有権が争われているいるわけではないからである。紛争の相手国は当面中国であるが、ここへの領有権は今後世界的に問題視されていくような気がしている。
それは、この島が果たして「領土としての島」なのかという領土としての基本が問われているからである。これまでに述べた①〜③までの島はアジア大陸に沿うように位置する日本列島との境界、言うなれば狭い海域にあって互いに近い距離にある両国間の紛争である。二つの国の中間近くにあって、どちらの国も歴史的にはそれほど重要視してこなかったのが、地下資源だの経済水域だのの利益が領土と密接につながってきたことから日の目を見るようになってきたと言うのが実感である。
ところが沖ノ鳥島は少し違う。この島は日本のはるか南、太平洋のど真ん中に位置している。この場で正確な位置を述べてもあんまり意味がないとは思うけれど、大雑把に言って九州とグアム島を結ぶほぼ中間に位置している。どうしてそれが領土問題にまでなっているのか。それはこの島が余りにも小さいからである。私が出かけていって確認したわけではないけれど、沖ノ鳥島は満潮時には北小島、東小島と呼ばれる小さな岩礁が僅かに頭を出すだけで、島のほとんどが水没してしまうのだそうである。島が存在してこその領土である。水没してしまうのならそこは島ではないことになるから領土問題など発生することなどまるでない。単なる海そのものだからである。
そうした水没の恐れがあるだろうことの事実は、日本政府が波で岩が水没してしまわないように波消しブロックやコンクリートなどで岩礁の周囲を固めていることからも理解できる。
そこで中国の主張である。「ここは島ではない。海である。この海域に及ぶような地域に日本の領土たる島は他に存在していないのだから、この海域は日本の領土や領海などの主権の及ぶことはなく単なる公海に過ぎない」。
波消しブロックなどによる補強がどこまで領土の保全と言えるのか、国際的に通用するのかなど私には分からない。それでも地球温暖化などで海水面の上昇が現実のものとされていて、南太平洋の島国のいつくかは国土が水没するとの危機感を国連などに訴えている。どこまで日本の領土としての主張が通るのか、いつまで通るのか、ことは中国一国との外交問題ではないように思えているのである。
2010.10.15 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ
日本の島が6000もあるのは日本の海域が広すぎることにも原因があるのではないかとこれと同時に発表したエッセイ(別稿「
日本の海域」参照)に書き、その海域をきちんと管理できないことも日本の領土問題につながる原因になっているのではないかと書いた。
ところで日本の領土問題は大きく北から順に「ロシアとの北方領土問題」、「韓国との竹島問題」、そして「中国との尖閣列島問題」、そして領土の概念からは少し外れるかも知れないが日本最南端を形成している「沖ノ鳥島問題」の四つに分けることができるだろう(これら4地域の位置については前述の「日本の海域」に載せた地図参照)。