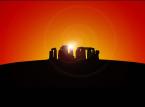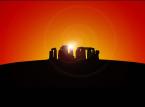オルフェウスの妻を求める心はいつになっても悲しい。オルフェウスはギリシャ神話の登場人物である。オイアグロスとカリオペの子(私の持っている「ギリシャ・ローマ神話」、トマス・ブルフィンチ著によると父の名はアポローンになっているが、定説ではオイアグロスのようである)オルフェウスは、アポロンからもらった竪琴の名手であり美しい妻エウリュデイケと結婚する。だが間もなく妻はその美貌ゆえに散歩中に羊飼いに言い寄られ、逃げ出そうとする途中で蛇に咬まれ死ぬ。
オルフェウスは様々な苦難をその竪琴の演奏を駆使することでくぐり抜け、たどり着いた黄泉の国の支配者ハデスに妻を連れ戻したいと懇願する。ハデスは「返してやろう。だが共に地上に着くまで決して彼女を振り返ってはならない」との条件をつけてその願いを聞き入れる。
だが、あと僅かで地上というときになってオルフェウスは彼女がすぐ後ろに着いてきているか心配になり、ついに振り向いてしまう。たちまち黄泉の国へと吸い込まれていく妻・・・。愛の深さは喪失の深さでもあろうか。彼は妻の存在を確かめるために振り向いたことで、愛しい妻を二度も失うことになったのである。
彼はその後、妻を慕うあまりすべての女からの求愛を退ける。しかし応えてくれないことへの恨みを抱いた女たちの手によって彼は八つ裂きにされ、川へと投げ込まれるのである。彼の竪琴はその後天に昇って「琴座」となる。
神話が人の世に生き続けていく背景には、そうした物語を支持する人びとの存在が欠かせないだろうし、その支持の根っこにはそうした物語のエキスが支持する人びとの生活の中に溶け込んでいることがあげられるだろう。
オルフェウスの過ちは「振り向いたこと」である。ほんの僅かそのまま地上へと向かって突き進むだけで、妻は彼の手へと確実に戻ってきたのだから・・・。どうして彼はハデスとの約束を違えてまで振り向いてしまったのだろうか。
その理由の一つに私は「不安」を見る。彼は妻の手を握って黄泉の国からの道を登ってきた。だから先に立つ彼にはその手の感触で妻が後ろについてきていることが分かったはずである。それにもかかわらず彼はその握りしめている手の先に妻がいることを自分の目で確かめずにはいられなかった。
見えているものが常に真実だとは限らないだろうけれど、だからと言って見えないものを信じることはもっと難しい。いま握っているのは本当に妻の手なのだろうか、その不安が彼にハデスとの約束を忘れさせた。疑心は本物の暗鬼を生むのである。一度芽生えた疑いの種は、たとえそれが小さなものであったとしてもたちどころに膨張しながら人の心を覆いつくしていく。もしかしたら握っているのは妻の手ではないかも知れない。他人の手、いやいやそれ以上に他人の手どころかその辺に落ちている木切れの類なのかも知れないではないか。死に物狂いの試練をくぐり抜け、やっと黄泉の支配者のもとから連れ戻した最愛の妻である。ここで間違ったらとりかえしのつかないことになる。
このオルフェウスを読んですぐ思い出すのが、イザナギとイザナミが日本国を作ったとする「古事記」の物語である。イザナミは火の神を産むと間もなく命を落とす。悲しんだイザナギが妻を黄泉へと迎えに行く。イザナミは「黄泉の国の食べ物を口にしたので戻れない」と言うが、懇願するイザナギを前にして「戻れるかどうか(黄泉の神に)聞いてくるのでその間私の姿を覗かないで欲しい」と約束させる。だがなかなか戻ってこない妻に不安を感じたイザナギは、約束を破って妻の部屋を覗く。そこにいるのは腐乱した醜悪な姿だった。逃げ出すイザナギ・・・。
この二つの物語はもしかしたら同一の起源を持つのかも知れないが、ともに夫が亡き妻を死の国へ迎えに行くこと、そして「見るな」の禁忌を「見てしまう」と言うほぼ同じようなストーリー構成になっている。黄泉の国と現世とは互いにどんなことがあっても相容れない世界なのかも知れない。恐らく死が生にもどることなど決してなかったのだろう。それでも人は死者の復活を願わずにはいられなかった。
それはいわば死が不可逆な絶対であることの裏返しであったのかも知れない。死者は亡霊となる以外、この世に戻ってくることなどあり得ないことを人は事実として知っていたと言うことでもあろう。
ならばなぜハデスはオルフェウスの願いを聞いて妻をこの世へ戻すことを許したのだろうか。もしかしたらハデスには死者を甦らせる思いなど最初からなかったのかも知れない。「振り向くな」の一言は人間には決して守ることのできない約束であることをハデスは最初から知っていたのかも知れない。
それは蜘蛛の糸にすがって地獄から天国へと上ってくるカンダタが後からついてくる多くの仲間たちに向かって放った悲痛な叫び(別稿「
蜘蛛の糸」参照)を、お釈迦様は最初から予定していたことと同じ意味を持っているのかも知れない。
こうした禁忌を巡る物語はあちこちの物語に見ることができる。ファウストは「刹那に向かって、『お前は美しい』」と叫ばなければ自らの魂を悪魔に引き渡すことはなかったのだし(別稿「
ファウスト、つまみ食い」参照)、ファウスト自身もそんな叫びなど決してしないだろうことを確信していたはずである。そのほかにもこれに似たストーリーは多くの神話や童話に同じような類型として見つけることができる。
仕事をしている私の姿を覗いてはいけない(別稿「
つるの恩返し」参照)、この箱を開けてはいけない(別稿「
浦島太郎」参照)、私の本性を他人(ひと)に話してはいけない(別稿「
雪女」参照、「王様の耳はロバの耳」)、どんなことがあっても声を上げてはならぬ(別稿「
杜子春(とししゅん)」参照)、母の教えを守り決して道草など食ってはいけない(「赤ずきんちゃん」)などなど、禁止とそれを破ってしまう人間の話などいくらでも思い出すことができる。
もっとも「ならぬ」とされることどもを、その通りに守ってしまったら物語としての展開はなくなってしまう。だとすればここは一つその約束を破らせることとし、そのペナルティとして新たな筋書きを求めたほうがいわゆる「面白い話」になるのかも知れない。それにしてもこうした「ならぬと言われた約束を破る」と言うパターンの物語がふんだんに見つかるということは、逆に人はそうした約束など守ることのできない存在なのだと言い切っているのと同じなのかも知れない。そうした約束の破綻を「嘘つき」と呼ぶか、はたまた「裏切り」と呼ぶかはとも角として、つまるところ人はこれしきの存在でしかない・・・と言うことでもあろうか。
ともあれ私も既に70歳。こうして僅かの仕事とエッセイの作成などを連ねている毎日であるが、この歳になると新しいことよりも振り返ることどもの多さに気づくことが多くなる。「振り返るな」はまさに至言ではあるけれど、振り返ることの滴りの中に身を置くこともひとつの居場所になっていることに気づく。だいいち過去を振り返ったところで、そのことで未来を変えられるほどの神通力など既に私から消え失せてしまっている。しかも過去の滴りが必ずしも甘いものだけとは限らないだろう。それでもその滴りに身を沈めることには、どこか安心へと私を誘ってくれるような気がする。たとえそれが「振り返るな」に反した苦さの残る結果をもたらすものであったとしても・・・。
2010.6.25 佐々木利夫
トップページ ひとり言 気まぐれ写真館 詩のページ